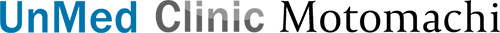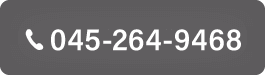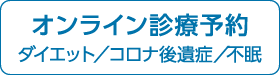慢性的な下痢でお困りではありませんか?
 下痢が続いているのに「そのうち治るだろう」と放置していませんか?慢性的に下痢が続いたり、何度も繰り返したりする場合、生活に支障をきたすだけでなく、背後に何らかの病気が隠れていることもあります。特に、数日以上に改善しない下痢や、他の症状を伴う場合は注意が必要です。当院では、患者様の症状や生活習慣を丁寧にお伺いし、必要に応じて検査を行った上で、下痢の原因を明らかにし、適切な治療を行っています。長引く下痢でお困りの方は、どうぞご相談ください。
下痢が続いているのに「そのうち治るだろう」と放置していませんか?慢性的に下痢が続いたり、何度も繰り返したりする場合、生活に支障をきたすだけでなく、背後に何らかの病気が隠れていることもあります。特に、数日以上に改善しない下痢や、他の症状を伴う場合は注意が必要です。当院では、患者様の症状や生活習慣を丁寧にお伺いし、必要に応じて検査を行った上で、下痢の原因を明らかにし、適切な治療を行っています。長引く下痢でお困りの方は、どうぞご相談ください。
下痢について
下痢は、便の水分量が多く、液状の便が何回も排泄される状態を指します。液状でなくても、いつもの便よりも柔らかい便を軟便と言います。水分量が大きく関係していて、理想的な便の目安はバナナのような便で、水分量は70~80%です。この水分量を超えると軟便になり、90%を超えると下痢とされています。
こんな下痢のときは受診が必要です
- 急に激しい下痢になる
- 便に血が混じっている
- 下痢症状に加えて嘔吐や吐き気症状がある
- 下痢症状に加えて発熱がある
- 時間が経過しても改善せず、悪化している
- 下痢に伴って脱水症状がある
- 便が出た後も腹痛がある
など、このような下痢の時は消化器内科専門医への受診が必要です。
下痢の種類
下痢の持続期間にもとづく種別
下痢には急性下痢症と慢性下痢症があります。急性下痢症はウイルスや細菌感染による胃腸炎が原因とされますが短期間で改善するのが特徴です。慢性下痢症は1カ月以上下痢が続く状態を言います。主な原因としては、過敏性腸症候群とクローン病や潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患があります。また、抗生物質などの薬の副作用や消化不良、食あたり、ストレスなども原因となります。慢性下痢症の中には、大腸がんが原因の場合もあるので、下痢症状が長期間続く場合は早めに医療機関を受診して下さい。
下痢の原因による種別
下痢は原因によって、「浸透圧性下痢」「滲出性下痢」「分泌性下痢」「機能性下痢」の4つに分類されます。このうち、浸透圧性・滲出性・分泌性の3つは、腸の炎症や吸収障害など器質的な異常に起因するのに対し、機能性下痢は検査で明らかな異常が見られない腸の機能的な不調によって起こるのが特徴です。
浸透圧性下痢
浸透圧性下痢とは、腸内に吸収されにくい物質が残ることで、水分が腸に引き寄せられ、便が軟らかくなるタイプの下痢です。乳糖不耐症や糖アルコールの過剰摂取、小腸の吸収障害などが原因となりやすく、腸内に残った未吸収の糖や電解質が水分を引き寄せることで起こります。この下痢は、食事を控えると改善しやすいのが特徴です。
分泌性下痢
分泌性下痢とは、腸の上皮から水分や電解質が過剰に分泌されることで起こる下痢です。コレラなどの感染性腸炎や、ホルモン産生腫瘍、一部の薬剤などが原因となります。このタイプの下痢は、食事を止めても改善しにくいのが特徴です。
滲出性下痢
滲出性下痢とは、腸の粘膜が炎症や潰瘍で傷つき、血液や粘液、たんぱく質などが腸内に漏れ出すことで起こる下痢です。潰瘍性大腸炎やクローン病、細菌性腸炎、虚血性腸炎などが原因となり、血便や粘液便、腹痛、発熱を伴うことが多いのが特徴です。
機能性下痢
機能性下痢とは、腸の運動が過剰になったりリズムが乱れたりすることで、腸内の水分が十分に吸収されないまま便として排出されるタイプの下痢です。主な原因としては、過敏性腸症候群(IBS)や甲状腺機能亢進症、糖尿病による自律神経障害などが挙げられ、腸に明らかな炎症や構造的な異常が見られない点が特徴です。このタイプの下痢では、食後すぐに便意を感じやすい、排便回数が多い、夜間は比較的症状が落ち着く、そしてストレスによって症状が悪化しやすいといった傾向があります。
下痢の原因となる生活習慣
暴飲暴食
食べ過ぎや飲み過ぎによって消化器に過度な負担がかかると、腸の働きが乱れ、未消化のままの食物が腸内にとどまり、結果として下痢を引き起こすことがあります。特に、早食いや一度に大量の食事を摂る習慣がある場合には、腸の蠕動運動(内容物を押し出す動き)が過剰になりやすく、便が速く移動することで水分が十分に吸収されず、下痢が生じやすくなります。
脂質の多い食事
脂質の多い食事は消化に時間がかかるうえ、腸を刺激しやすいため、腸の蠕動運動が活発になりやすく、結果として下痢を引き起こすことがあります。とくに、油を多く使った揚げ物や脂肪分の多い加工食品・外食を頻繁に摂取する習慣がある方は、腸内環境が乱れやすく、下痢を繰り返す傾向があるため注意が必要です。
精神的なストレス
精神的なストレスは自律神経の働きを乱し、腸の運動が過敏になる一因となります。たとえば、過敏性腸症候群(IBS)では、不安や緊張などの心理的負荷によって下痢などの症状が現れることがあります。このように、心と腸の働きは密接に関係していることが広く知られています。
体の冷え
気温の低下や薄着、冷房の強い場所などの影響で体が冷えると、お腹まわりの血行が悪くなり、それによって腸の働きが低下することがあります。このような状態では、腸の蠕動運動(内容物を移動させる動き)が乱れ、水分の吸収が不十分となり、下痢につながることがあります。特に女性は冷えに敏感な傾向があるため、腹部を冷やさないように注意することが大切です。腹巻きの使用や温かい飲み物を取り入れて体を温めることが、冷えによる下痢の予防に役立つことがあります。
冷たい飲み物の摂取
冷たい飲み物を短時間で大量に摂取すると、腸が冷やされて蠕動運動(腸の動き)が急激に活発になることがあり、その影響で水分が十分に吸収されないまま便として排出され、下痢を引き起こすことがあります。特に、夏の暑い時期や空腹の状態で冷たいものを摂ると、腸への刺激が強くなり、下痢が起こりやすくなる傾向があります。
睡眠不足
十分な睡眠が取れない状態が続くと、自律神経の調整が乱れ、それにより腸の機能にも影響が及ぶことがあります。その結果、腸内環境が悪化したり、精神的ストレスがたまりやすくなったりして、下痢やお腹の不快感といった症状の一因になることがあります。
過剰なカフェイン摂取
カフェインには腸の蠕動運動を促進する働きがあり、過剰に摂取すると腸の内容物が通常よりも早く移動し、水分が十分に吸収されないまま便として排出されることで下痢を引き起こすことがあります。特に、コーヒー、エナジードリンク、緑茶などを頻繁に飲む習慣がある方は、腸への刺激が強くなりやすいため注意が必要です。
過度な飲酒
アルコールには腸の粘膜を刺激する作用があり、その影響で腸内の水分調節機能が乱れ、下痢を引き起こすことがあります。なかでも、ビールやワインなどを一度に多量に飲んだ場合には、胃や腸に炎症を生じやすくなり、アルコール性胃腸炎と呼ばれる状態を伴うこともあります。
喫煙
喫煙によって体内に取り込まれるニコチンは、腸の蠕動運動(内容物を送り出す動き)を活性化させる作用があり、その影響で腸内の内容物が通常よりも早く通過し、水分の吸収が不十分なまま下痢になることがあります。とくに空腹時の喫煙や過剰な本数の喫煙は、腸への刺激が強くなりやすく、下痢を引き起こしやすいとされています。
薬の副作用
市販薬や処方薬の中には、日常的によく使われるものでも下痢の副作用がみられることがあります。たとえば、抗生物質は腸内の善玉菌まで減らしてしまい、腸内環境のバランスが崩れることで下痢を引き起こすことがあります。特に風邪や咽頭炎などで処方されるペニシリン系やマクロライド系の抗菌薬が代表的です。また、痛み止め(NSAIDs)や鉄剤、一部の胃薬(制酸剤)なども、人によっては消化器に刺激を与え、下痢を起こす場合があります。薬の副作用による下痢が疑われる場合は、自己判断で服薬を中断せず、医師や薬剤師に相談することが重要です。
止まらない下痢の対処方法
急性下痢の場合
突然始まって止まらない下痢の多くは、ウイルスや細菌の感染、または一時的な食あたりが原因で生じることが一般的です。通常は1〜2日ほどで自然におさまることが多く、まずは安静にして体力の回復を優先することが大切です。ただし、発熱・嘔吐・血便を伴う場合や、下痢が24時間以上続く場合には、感染性胃腸炎などの可能性があるため、早めに医療機関を受診しましょう。また、市販の下痢止めを自己判断で使用すると、原因となるウイルスや細菌の排出が妨げられ、かえって症状が長引くことがあるため、注意が必要です。
慢性下痢の場合
下痢の状態が数週間以上続く場合には、過敏性腸症候群(IBS)や炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病など)、あるいは服用薬による影響などが関係している可能性があります。慢性的な下痢は、脱水や電解質の乱れ、栄養不良につながるリスクがあるため、放置せずに早めに医師の診察を受け、必要に応じて内視鏡検査や血液検査などを受けることが大切です。また、食事内容の調整、十分な睡眠の確保、ストレスの軽減など、生活習慣を整えることによって、症状が改善するケースも見られます。
水分補給
下痢が続くと、体内から水分とともにナトリウムやカリウムなどの電解質も多く失われるため、脱水状態に陥るリスクが高まります。このような脱水を防ぐには、こまめに水分を補給することが重要です。とくに適しているのは、電解質と糖分のバランスがとれた経口補水液(ORS)や、軽度の脱水対策として利用されるスポーツドリンクなどです。一方で、カフェインやアルコールを含む飲料には利尿作用があり、かえって水分の排出を促してしまう可能性があるため、下痢が続いている間は控えるようにしましょう。
食べ物・飲み物
下痢の際には、胃腸への負担が少ない食品を選ぶことが大切です。具体的には、おかゆややわらかいうどん、バナナ、すりおろしたリンゴ、にんじんを使ったスープなどが適しています。これらの食品は消化がよく、腸を刺激しにくいとされています。一方で、脂質の多い料理や香辛料の強い食事、冷たい飲料、牛乳などの乳製品は腸の働きを乱すことがあるため、下痢が続いている間は控えたほうがよいでしょう。なお、食欲がないときは、無理に食事を取る必要はありません。その場合は、まず脱水を防ぐために水分補給を優先することが重要です。
市販薬の使用
下痢がつらいときに市販の下痢止めを使うことがありますが、使用には注意が必要です。感染症による下痢の場合、体内のウイルスや細菌を排出することが大切で、無理に下痢を止めると症状が悪化することがあります。一時的に症状を抑えたいときは、薬剤師に相談し、添付文書を確認して正しく使いましょう。下痢が長引く場合や、発熱・血便を伴うときは、早めに医療機関を受診してください。
下痢を引き起こす疾患とは?
ウイルス性胃腸炎
胃腸がウイルス感染することで、下痢や吐き気、嘔吐、発熱、腹痛などが起こる病気です。ロタウイルスやアデノウイルス、ノロウイルスなどが原因です。
過敏性腸症候群
主な原因はストレスで、腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)に異常が起こる病気です。慢性的な下痢や、逆に慢性的な便秘、さらに下痢と便秘を交互に繰り返すなどの症状が起こります。
クローン病
口から肛門までの消化管のあらゆる場所で炎症や潰瘍が起こる難治性の病気です。小腸や大腸に潰瘍ができることがあるため、消化・吸収が悪くなって下痢を起こします。
潰瘍性大腸炎
大腸の粘膜で慢性的な炎症が起こり、びらんや潰瘍ができる難治性の病気です。長期間下痢や腹痛が続き、粘血便が症状として特徴的です。
大腸がん
腸の内腔が狭くなるため、便通が悪くなり便秘がちになります。便秘と下痢を繰り返したり、下痢が多くなることもあります。
虚血性腸炎
虚血性腸炎とは、大腸の一部で一時的に血液の流れが悪くなることによって、腸の粘膜に炎症や障害が生じる疾患です。典型的な症状としては、左側の腹部から下腹部にかけての痛み、下痢、そして血便などがあげられます。大腸への血流が不十分になることで、酸素や栄養が粘膜に行き渡らなくなり、その結果として腸の組織に損傷が起こり、これらの症状が引き起こされます。
慢性膵炎
慢性膵炎とは、膵臓に炎症が繰り返し起こることで、組織が徐々に硬く線維化し、膵臓本来の機能が低下していく疾患です。この膵臓機能の低下、とくに消化酵素の分泌量が減ることで、食べ物の消化や栄養の吸収がうまくいかなくなります。その結果、脂肪や栄養素が未消化のまま腸に送られ、腸内での水分吸収が不十分になるため、脂肪便や慢性的な下痢を引き起こす原因となります。とくに脂っこい食事の後に下痢が続くような場合は、慢性膵炎の可能性も考えられるため注意が必要です。
下痢の検査方法
当院では、丁寧な問診に加えて、必要に応じて血液検査や腹部エコー検査を実施し、下痢の原因を総合的に評価します。なお、大腸内視鏡検査(大腸カメラ)が必要と判断される場合には、提携する消化器内視鏡専門の医療機関をご紹介いたします。下痢の背景に大腸がんなどの重大な疾患が潜んでいるケースもあるため、症状が長引く場合や異常を感じる場合は、早めの受診をおすすめします。
また当院では、腸内フローラ検査としてサイキンソー社の「Mykinso」を導入しています。この検査は、下痢の原因精査や腸内環境の評価に役立ち、慢性的な下痢にお悩みの方にとって有用です。体調管理や今後の治療方針を立てる上でも有益ですので、必要に応じて検査をご検討ください。
下痢の治療方法
急性下痢症の場合、ウイルスや細菌感染による胃腸炎が原因であることが多いので、整腸剤を用いた治療が一般的です。必要に応じて抗生物質を投与していきます。
慢性下痢症の場合は、大腸内視鏡検査など各種検査を行って原因を特定していきます。原因に応じて適切な治療を行います。
器質的疾患が否定された場合は、過敏性腸症候群が考えられるため、これまでの生活習慣を改善し、ストレス解消のアドバイスと同時に内服治療をしていきます。
よくある質問
緑色の下痢が出るのはどのような理由がありますか?
便が緑色になるのは、腸の中を内容物が早く通過しすぎたことで、胆汁が十分に分解されずに排出されることが一因です。特に下痢によって腸の通過時間が短縮されると、便に緑がかった色が残ることがあります。また、鉄剤を内服している方や、緑色の着色料を含む飲食物を摂取した場合にも、便の色が変化することがあります。もし発熱や腹痛などの症状を伴う場合には、感染性の疾患の可能性もあるため、早めの受診が望ましいです。
女性に多い下痢の原因にはどんなものがありますか?
女性は冷えやホルモンバランスの変化、自律神経の乱れなどの影響を受けやすく、下痢が起こりやすい傾向があります。たとえば、冷たい飲み物や冷房による体の冷えは腸の働きを低下させます。また、生理前後のホルモンの変動やストレスによって腸の動きが過敏になり、過敏性腸症候群のような症状が出ることもあります。さらに、極端なダイエットや偏った食生活によって腸内環境が乱れ、下痢の原因になることもあります。気になる症状が続く場合は、生活習慣の見直しと医療機関への相談が大切です。
急に下痢になるのはどうしてですか?
突然の下痢は、多くの場合ウイルスや細菌による胃腸の感染、あるいは食あたりなどが関係しています。そのほか、精神的な緊張やストレス、冷たい飲食物の摂取、過剰な飲食が腸を刺激し、急に下痢を引き起こすこともあります。通常は一過性で自然に回復することが多いですが、症状が激しかったり長引いたりする場合は、速やかに医療機関での診察を受けることが大切です。
下痢のときに使える薬には何がありますか?正露丸を使っても大丈夫ですか?
市販の下痢止めとしては、ロペラミド(ロペミンなど)や整腸剤がよく用いられます。正露丸も一部の急性の下痢に効果があるとされていますが、感染性の下痢では体内の原因物質を排出することが優先されるため、使用が適さないケースもあります。自己判断で服用せず、薬剤師や医師に相談したうえで適切に使うようにしましょう。
下痢を早く治すにはどうすればよいですか?
まずはしっかりと休息をとり、腸への負担を減らすことが基本です。水分を十分に補いながら、消化の良い食べ物を少量ずつ摂取しましょう。下痢が数日続く、または症状が悪化するようであれば、速やかに医師の診察を受けて、必要な検査や治療を受けることが重要です。
下痢は我慢せずに出した方がいいのでしょうか?
感染や食あたりが原因で下痢が起きている場合、腸が異物を排出しようとしているため、無理に排便を我慢するよりも自然に出すことが望ましいです。ただし、脱水を防ぐためには水分の補給が不可欠です。下痢が激しく、腹痛や発熱を伴う場合には、医療機関での診察が必要です。
下痢のときは食事を控えたほうがよいですか?
無理に食べる必要はありませんが、完全な絶食は避けた方がよいでしょう。おかゆやすりおろしリンゴ、にんじんを煮たスープなど、消化にやさしいものを少量ずつ摂ることで、体力の回復に役立ちます。食欲がないときは、まず水分と電解質の補給を優先してください。
下痢のときにポカリスエットを飲んでも問題ありませんか?
軽度の脱水対策としては、ポカリスエットのようなスポーツドリンクは適しています。ただし、糖分が多く含まれているため、大量に一度に飲むのではなく、少しずつこまめに摂取することが望ましいです。中等度以上の脱水が疑われる場合には、経口補水液(ORS)の使用が推奨されます。
下痢のときにお腹が鳴るのはなぜですか?
お腹がゴロゴロ、またはギュルギュルと音を立てるのは、腸の動きが活発になっているサインです。下痢のときは腸の内容物が通常よりも早く移動するため、その過程で音が発生しやすくなります。これは腸が刺激に反応して活動している状態と考えられます。
下痢が何日続いたら医療機関を受診すべきですか?
一般的には、下痢が2~3日経っても改善しない場合や、発熱、血便、強い腹痛、吐き気、体重減少などの症状を伴う場合には、早めに受診することをおすすめします。1カ月以上下痢が続いている場合は慢性下痢と考えられ、炎症性腸疾患などの可能性もあるため、専門的な検査が必要です。
肛門から水のような液体が出てくるのはなぜでしょうか?
肛門から水状の分泌物が出る場合、下痢そのものか、あるいは腸の粘膜から分泌される粘液が原因であることが考えられます。腸の炎症(たとえば潰瘍性大腸炎や感染性腸炎)や、痔、肛門周囲の異常でも同様の症状が現れることがあります。続くようであれば、消化器科など専門の診察を受けるようにしてください。