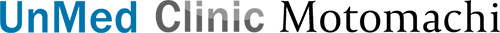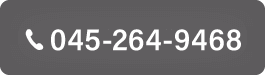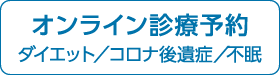食欲不振の症状でお困りの方へ

食事をとる気が起こらない、極端に食事が偏る、空腹を感じないなど、食事の意欲を失う・食欲がわかない食欲不振の状態は、ストレスや心労、消化器疾患、薬の副作用など様々な原因によって起こります。食事は、毎日の生活の中で欠かすことのできないものです。食欲不振の状態が続くと、体が必要な栄養を十分に摂取することができなくなる恐れがあります。
また、バランスの悪い偏った食習慣は、何らかの病気発症リスクにつながることもあります。食欲不振の状態は、そのまま放置せずに原因を調べて適切な治療を行いましょう。
このような食欲不振の症状はありますか?
- 数週間から長期にわたって食欲がわかない状態が続く
- 食事が面倒くさいと感じる
- 食欲不振が長期間続いて体重が減ってきた
- 食事をすることをたびたび忘れてしまう
- あっさりしたものばかり食べる等、食事が偏っている
- 食べ物の味がしない・美味しいと感じない
- 胃痛や腹痛などの症状があって食欲がわかない
上記の症状でお困りの方は、当院へご相談ください。
食欲不振の原因とは
精神的なストレス
心のストレスは、食欲低下の一因となることがあります。たとえば、仕事上の緊張や人間関係の悩み、将来への不安が長く続くと、自律神経の働きが乱れ、胃の動きが鈍くなりやすくなります。その影響で空腹感を感じにくくなり、「気分が落ち着かない」「食事をしたくない」といった状態になり、結果的に食べる量が減ることがあります。このようなストレスに起因する食欲不振は、痛みや発熱といった明確な症状が現れにくく、自覚しにくい場合があります。一時的であれば自然に回復することもありますが、食事が十分に摂れない日が続いたり、体重が急に減少したりする場合には、医療機関で相談することが大切です。
生活習慣の乱れ
生活習慣の乱れは食欲低下を引き起こすことがあります。特に、睡眠不足・運動不足・不規則な食事時間は、体のリズムや消化機能に悪影響を与えやすい要因です。睡眠が足りないと自律神経やホルモンのバランスが乱れ、胃腸の働きが鈍くなって空腹感を感じにくくなります。運動不足も代謝を低下させ、自然な空腹感が減る一因となります。また、食事の時間が毎日ばらばらだったり、朝食を抜く習慣があると、体が食事のタイミングを把握できず、食欲のリズムが崩れてしまいます。このような生活リズムの乱れは、空腹を感じて食事をとり、消化するという本来の流れを妨げてしまい、その結果として食欲が落ちることがあります。食欲を保つためには、日々の生活を規則正しく整えることが大切です。
暑さ・夏バテ
暑さや夏バテが原因で食欲が落ちることがあります。特に梅雨から夏にかけての蒸し暑い時期は、体に負担がかかりやすく、食事が進まないと感じる方が増えます。高温多湿の環境では、体温調節にエネルギーを使い、自律神経が乱れやすくなります。その結果、胃腸の働きが低下し、空腹感が起こりにくくなったり、だるさや胃もたれを感じやすくなります。また、冷たい飲み物やあっさりした食事が続くと栄養が偏り、さらに食欲が低下することもあります。睡眠不足や気温差による疲労も、夏バテの一因となります。
薬の副作用
服用している薬の副作用で、食欲が低下することがあります。たとえば、抗菌薬や鎮痛薬(NSAIDs)は胃の不快感や吐き気を引き起こし、食事がとりにくくなることがあります。さらに、抗うつ薬や睡眠薬、降圧薬の一部では、口の乾きや倦怠感、味覚異常などがみられ、これが食欲不振につながる場合もあります。薬の影響による症状には個人差があるため、服用後に食欲が大きく落ちたと感じた場合は、自己判断で中止せず、医師や薬剤師に相談しましょう。
加齢
加齢にともなう体の変化によって食欲が落ちることがあります。たとえば、味覚や嗅覚が鈍くなると食事の楽しみが減り、食べる意欲がわきにくくなります。また、唾液の分泌が減ることで口の中が乾きやすくなり、飲み込みにくさや食事の煩わしさを感じることもあります。さらに、胃腸の動きがゆるやかになることで満腹感を得やすくなり、消化にも時間がかかるため、自然と食事量が減りがちです。加えて、運動量の低下や孤立感、気分の落ち込みも、食欲に影響を与える要因です。このように、加齢による心身の変化は無理のない範囲で起こる食欲の低下です。無理に食べようとせず、食べやすい工夫や快適な食環境づくりを心がけることが大切です。
ホルモンバランスの変動
ホルモンバランスの変化によって食欲が落ちることがあります。たとえば、女性は月経周期、妊娠、更年期などでホルモンが大きく変動しやすく、それに伴って気分や消化機能が不安定になり、食欲が低下することがあります。また男性でも、中高年以降にテストステロンが減少する「男性更年期障害」が見られることがあり、疲労感や抑うつ傾向から食欲が落ちるケースがあります。さらに、ストレスや生活習慣の乱れもホルモンや自律神経に影響し、食欲不振の原因になります。ホルモンによる変化は一時的なこともありますが、長く続く場合は医師への相談が大切です。
男性更年期障害とは
男性も40〜50代以降になると、加齢にともなって男性ホルモン(テストステロン)の分泌量が少しずつ減少していきます。このホルモンの低下により、身体的・精神的な不調が現れる状態を「男性更年期障害(加齢男性性腺機能低下症候群、LOH症候群)」と呼びます。この障害に関連する主な症状には、以下のようなものがあります。
- 疲労感や活力の低下
- 気分の落ち込みやイライラ
- 集中力や意欲の低下
- 睡眠の質の悪化
- 顔のほてり、発汗が増える
- 筋力や性機能の衰え
- 食欲不振や体重の減少
テストステロンの分泌は、加齢だけでなくストレスや生活習慣の影響も受けやすいため、忙しさや精神的な負荷が強いときに症状が悪化することもあります。また、女性の更年期と違って発症時期に個人差があり、症状がゆっくり進行するため、自覚しにくいのが特徴です。日常生活に支障が出るような状態が続く場合には、泌尿器科や男性更年期専門外来で相談することが勧められます。血液検査でテストステロンの値を確認し、必要に応じてホルモン補充療法や生活習慣の見直しなどが行われます。
食欲不振が起こる主な疾患
風邪・インフルエンザ
風邪やインフルエンザはウイルスによる感染症で、発熱やのどの痛み、咳、倦怠感などの症状がみられます。こうした体調不良が続くと、食欲が落ちることはよくあります。発熱時は体がウイルスと戦うためにエネルギーを使い、消化機能が一時的に低下することで、空腹感が起こりにくくなります。特にインフルエンザでは、頭痛や筋肉痛、強いだるさが加わり、より顕著な食欲不振を引き起こすことがあります。ただし、このような食欲低下は一時的なことが多く、回復とともに改善します。ただし、高熱が続いたり水分や食事が摂れない状態が長引く場合は、脱水や体力低下に注意が必要です。風邪やインフルエンザにかかった際は、無理に食べず、消化の良いものを少しずつとり、水分補給をこまめに行うことが大切です。
うつ病
うつ病は、気分の落ち込みや意欲の低下が続く精神疾患で、心だけでなく体にも影響を及ぼします。症状のひとつとして、食欲の低下がよくみられます。これは、脳内の神経伝達物質(セロトニンやノルアドレナリンなど)の働きが乱れることで、食欲や消化機能の調整にも影響が出るためと考えられています。その結果、「食事をとる気がしない」「味を感じにくい」といった状態が起こり、食事量や体重が減ることもあります。また、不眠や疲労感、人との関わりがつらいなどの症状が重なることで、さらに食欲が落ちやすくなります。一方で、うつ病の中には過食が目立つタイプもあるため、必ずしも全員が食欲低下を伴うわけではありません。「最近食べられない」「急に体重が減った」などの変化に気づいたら、早めに医療機関に相談することが大切です。
機能性ディスペプシア
機能性ディスペプシア(FD)は、胃に不快感があるにもかかわらず、内視鏡などの検査で異常が見つからない消化管の機能的な疾患です。食後の胃のもたれ、少量で満腹になる感じ(早期飽満感)、みぞおちの痛みや熱感などが代表的な症状です。これらの症状が続くと、食事が負担に感じられ、食欲が落ちてしまうことがあります。原因としては、胃の動きの低下や感覚過敏、自律神経の乱れ、ストレスなどが関与していると考えられています。検査で異常がないのに食欲不振が続く場合は、機能性ディスペプシアが原因の可能性があるため、早めの受診が大切です。
慢性胃炎・萎縮性胃炎
ピロリ菌に感染することで起こる慢性胃炎や萎縮性胃炎を長く放置していると胃の消化機能が低下して食欲不振の症状が現れることがあります。
逆流性食道炎
逆流性食道炎は、胃酸や胃の内容物が食道へ逆流し、食道の粘膜に炎症が起きる疾患です。主な症状には、胸やけ・喉の違和感・酸っぱい液が上がる感じ(呑酸)・みぞおちの痛みなどがあり、これらが続くと食事がつらく感じられ、食欲が低下することがあります。特に食後は胸のつかえや不快感が出やすく、「食べると苦しい」「また症状が出そう」と感じて食事を避けがちになります。また、夜間の逆流や慢性的な不快感があると、睡眠不足や疲労感にもつながり、さらに食欲が落ちやすくなります。この疾患は、加齢・肥満・姿勢・脂っこい食事・ストレスなどが影響して発症しやすく、治療には胃酸を抑える薬(PPI・H2ブロッカー)や生活習慣の見直しが効果的です。食欲不振に加え「胸がムカムカする」などの症状が続く場合は、逆流性食道炎の可能性もあるため、早めの受診が大切です。
胃潰瘍・十二指腸潰瘍
ピロリ菌感染、非ステロイド系消炎鎮痛剤の服用、慢性的なストレスなどが原因で胃や十二指腸の粘膜が胃酸でただれて潰瘍ができる状態です。胃潰瘍は食事中から食後にかけてみぞおちに痛みが現れます。十二指腸潰瘍は空腹時や早朝にシクシクとみぞおちの辺りが痛みます。食事をすると痛みが治まります。みぞおちの痛みの他に、食欲不振や胸やけ、膨満感などの症状が現れます。
糖尿病
糖尿病は、血糖のコントロールがうまくいかなくなる慢性的な疾患で、病状が進むにつれて食欲が低下することがあります。その一因が、高血糖が続くことで胃の運動機能が低下する「糖尿病性胃不全(胃排出遅延)」です。この状態では、食べたものが胃にとどまりやすくなり、胃の不快感や吐き気、すぐに満腹になる感じが起こりやすく、食事量が減る原因になります。さらに、糖尿病性腎症や脱水、ケトアシドーシス(血液のpHが酸性に傾く急性合併症)といった糖尿病に関連した症状や、血糖変動による倦怠感や精神的な負担も、食欲の低下に関係しています。食欲不振が長く続くと、栄養不足や低血糖につながる可能性があるため、「食事が摂れない」「食後に気分がすぐれない」といった症状があれば、早めに医師へ相談することが大切です。
肝疾患(肝炎・肝硬変・肝がん)
肝臓は、代謝や解毒など多くの重要な役割を担う臓器です。肝炎・肝硬変・肝がんなどで肝機能が低下すると、代謝バランスが乱れ、食欲が落ちやすくなります。慢性肝疾患では、だるさ・吐き気・腹部膨満感が重なり、食事を摂りづらくなることがあります。肝硬変が進行すると、腹水や胃腸のうっ血、味覚異常が起き、さらに食欲が低下します。また、肝がんでは、炎症や不安感が影響して、体重減少や顕著な食欲不振を伴うことがあります。このような食欲低下を放置すると栄養不足や体力低下につながるため、早めに消化器内科などでの相談が必要です。
神経性食欲不振症(拒食症)
胃がん
初期の胃がんは自覚症状が乏しいことが多いですが、進行するに従い徐々に『サイトカイン』という物質が生成されて、胃の機能が低下していくと食欲不振の症状が現れます。
慢性腎臓病・腎不全
慢性腎臓病や腎不全では、腎機能の低下によって老廃物が体内にたまり、吐き気・口の不快感・味覚異常などが起こりやすくなります。これが原因で、食事が進まなくなり、食欲が落ちることがあります。また、貧血や倦怠感、むくみといった症状も食欲不振に影響します。病状が進み透析が必要になると、食事制限が増えるため、さらに食べにくくなることがあります。長期的な食欲不振は栄養不足や体力低下を招くため、体調に合った食事管理が重要です。
慢性膵炎
慢性膵炎は、膵臓の炎症が長く続き、消化機能が低下する疾患です。食後の腹痛やお腹の張り、下痢、体重減少などが続き、食欲が落ちやすくなります。また、食後に腹部から背中への痛み(放散痛)がみられることがあり、痛みを避けて食事を控える方もいます。進行すると、血糖調整が乱れ、倦怠感や低血糖も加わってさらに食欲が低下することがあります。
胆のう炎・胆石症
胆のう炎や胆石症は、胆のうに炎症や胆石が生じることで、消化機能に支障をきたす疾患です。とくに脂質の多い食事の後に、右上腹部の痛みや吐き気、腹部の張りといった症状が現れ、それが食欲の低下につながることがあります。炎症が進行している場合には、痛みが右肩や背中(肩甲骨付近)へと広がることがあり、体を動かすのが辛くなる方もいます。また、発熱や全身のだるさ、嘔吐を伴うこともあります。胆のうの機能が低下すると、胆汁の分泌や流れに影響が出て、食べ物の消化が不十分になりやすくなります。この結果、食後の不快感から自然と食事量が減ってしまうことがあります。症状が慢性化すると、「食べると痛くなるのでは」といった不安や、習慣的な食事制限によって、持続的な食欲不振に陥る方もいます。
甲状腺機能低下症
甲状腺の機能が低下すると、ホルモンの分泌する働きが弱くなり食欲不振や体重減少などの症状が現れます。この疾患は、血液検査ですぐに判定ができます。食欲不振の他に体のだるさ、倦怠感、鬱のような症状がある方は、甲状腺機能の検査を受けましょう。
食欲不振の検査
食欲不振の原因を把握するため、まずは「症状が始まった時期」「体重の変化」「服用中の薬」「過去の病歴」などを詳しくお聞きします。また、心理的なストレスや生活環境の変化が関係することもあるため、日常の過ごし方などについても丁寧に確認します。必要に応じて血液検査や腹部エコー検査などを行い、甲状腺機能や肝・腎機能、栄養状態などを調べます。消化器疾患や内視鏡検査(胃カメラ)が必要と判断される場合には、提携している医療機関をご紹介し、精密検査を受けていただく体制を整えています。「最近食欲がわかない」「食べると気分が悪くなる」といった症状がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
食欲不振の治療
食欲不振の原因は、様々です。まずは、食欲不振の症状が現れた時期や期間、具体的な症状について詳しくお伺いします。普段服用しているお薬の有無や既往症について確認しながら、薬の副作用が原因と考えられる場合は、食欲不振の症状が起こりにくい薬剤への変更などを検討します。
食欲不振の治療は、基本的に原因や症状に合わせた適切なお薬を処方いたします。急性胃腸炎による食欲不振の場合は、整腸剤や制吐剤などを用いて治療を行います。脱水や栄養障害などがみられる場合は点滴治療を行っていきます。過度なストレスが原因と考えられる場合、ストレスをうまく解消していくことで症状が改善につながります。
漢方薬による治療
食欲不振は、胃腸の機能低下や心理的ストレス、全身の疲労感などが影響するほか、機能性ディスペプシア、慢性膵炎、うつ病といった疾患が関係していることもあります。検査で明確な異常が見つからない場合でも、不調が続いて日常生活に支障をきたしている方もいらっしゃいます。こうした背景のあるケースに対して、当院では症状や体質に応じて漢方薬を用いた治療を行うことがあります。たとえば、胃のもたれや吐き気が気になる方には「六君子湯(りっくんしとう)」、全身の疲労感が強い方には「補中益気湯(ほちゅうえっきとう)」、喉のつかえ感や不安感を伴う方には「半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)」を使用することがあります。漢方薬は、同じ「食欲不振」という症状でも、その背景にある体質や体調によって選ぶ薬が異なります。当院では、症状の経過や体調を丁寧にお聞きしながら、個々に合わせた治療をご提案します。気になる症状があれば、お気軽にご相談ください。
よくある質問
お腹はすくのに食べられないのはなぜですか?
空腹感があるのに食事が進まない場合、胃の働きが弱っていたり、自律神経の乱れが関与している可能性があります。自律神経は消化機能の調整を担っているため、ストレスや緊張が強いと胃腸の動きが鈍り、少し食べただけで満腹感を感じたり、食後に不快感が出ることがあります。機能性ディスペプシアや心理的要因が背景にあることもあるため、症状が続くようであれば医療機関への相談をおすすめします。
食欲不振と胃痛が同時にある場合、どんな原因が考えられますか?
胃の痛みと食欲低下が同時に現れる場合、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、慢性胃炎、逆流性食道炎、機能性ディスペプシアなどの消化器疾患が考えられます。これらは胃や腸の粘膜に炎症や障害があることで、食事を摂るのがつらくなり、食欲が落ちてしまうことがあります。早期の診断と治療が大切ですので、医療機関での受診を検討してください。
子供の食欲不振の原因にはどのようなものがありますか?
お子様の食欲が落ちる原因には、風邪や胃腸炎などの一時的な体調不良、夏の暑さによる体力低下、心理的ストレス、生活リズムの乱れなどがあります。好き嫌いが多い場合や偏食によって、必要な栄養が不足してしまうこともあります。成長に影響を与えないよう、様子を見ながら必要に応じて小児科を受診しましょう。
原因不明の食欲不振が続くときは、どんな病気の可能性がありますか?
はっきりした原因がわからないまま食欲不振が続く場合、機能性ディスペプシアやうつ病、糖尿病、甲状腺機能低下症、肝臓疾患、胃がんなどが潜んでいる可能性があります。これらの疾患は初期には症状が目立たないこともあり、長く続く場合や体重の減少が見られる場合は、医療機関での検査を受けることが重要です。
食欲不振と吐き気がある場合は、何科を受診すればよいですか?
食欲の低下と吐き気が同時にある場合は、まずは内科または消化器内科の受診を検討しましょう。胃腸の不調のほか、薬の影響やホルモンの乱れ、精神的なストレスが関係していることもあるため、幅広い視点で診察できる診療科が適しています。
食欲不振・吐き気・微熱の症状があるとき、どんな疾患が疑われますか?
これらの症状が同時に見られる場合、風邪やインフルエンザなどの感染症、胃腸炎、肝炎、膵臓の炎症、腎臓疾患、またはホルモンや精神的な要因などが関連している可能性があります。発熱を伴う場合は感染症の可能性があるため、できるだけ早めに医療機関を受診することが望ましいです。
食欲不振が何日続いたら注意が必要ですか?
食欲がない状態が3日以上続く場合や、1週間経っても回復しない場合は、注意が必要です。特に、体重が減ってきた、吐き気やだるさなどの症状があるときは、体に何らかの異常がある可能性があるため、早めに医師に相談してください。
食欲が落ちたときは、何を食べるとよいですか?
食欲がわかないときは、無理にたくさん食べず、消化にやさしい食べ物(おかゆ、うどん、スープ、豆腐、やわらかい果物など)を少量ずつとるのがよいでしょう。胃に負担のかかる脂っこいものや冷たい飲食物は避け、水分補給もしっかり行うようにしてください。
食欲不振を放置するとどうなりますか?
食欲が落ちたままの状態をそのままにしていると、栄養が不足し、体力の低下や免疫機能の低下につながる可能性があります。さらに、筋肉量が減るなど全身の機能にも影響が及ぶおそれがあります。食欲不振が長引く場合は、早めの受診が重要です。
食欲不振を改善するにはどうすればよいですか?
生活習慣を見直すことが、改善への第一歩です。規則正しい生活と十分な睡眠、バランスのよい食事、軽い運動を心がけることで、自律神経や消化機能が整いやすくなります。原因となる疾患がある場合には、その治療が必要です。状況に応じて漢方薬の使用が効果的なこともあるため、医師にご相談ください。
食欲不振で病院を受診するタイミングは?
数日間にわたって食欲が戻らない、あるいは体重減少、吐き気、腹痛、発熱、倦怠感などの症状が一緒に見られる場合は、早めの受診をおすすめします。早期に原因を特定して適切な治療を行うことで、症状の悪化を防ぐことができます。