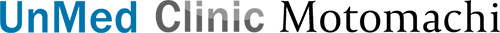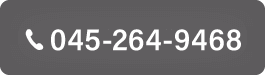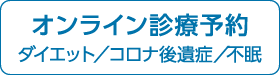インフルエンザウイルスは家庭内や職場で急速に感染拡大する可能性があり、特に受験生や免疫力が低下している方にとって予防が重要です。ご家族、同居の方にインフルエンザ感染者が発生した場合(濃厚接触者)、感染拡大しないように発症を抑制する目的で抗インフルエンザ薬の服用が可能です。
当院でも、抗インフルエンザ薬の予防投与を開始することに致しました(自費診療)。
予防投与は基本的にインフルエンザ患者との接触から48時間以内に開始します。
対象者
予防目的とした適応としては、「インフルエンザウイルス感染症を発症している患者の同居家族又は共同生活者である下記の者」を対象としています。
- 高齢者(65歳以上)
- 慢性呼吸器疾患又は慢性心疾患
- 代謝性疾患患者(糖尿病等)
- 腎機能障害患者
※服用をご希望される場合は、「健康保険適応外」となります。
費用(税込)
当院でのお支払いは診察代および処方箋代で税込み約3,500円程度です。
院外処方となるため、薬剤代は薬局でお支払いください。
※オンライン診療の場合は、別途、
推奨薬剤の用法・特徴
ゾフルーザ®(バロキサビル マルボキシル)
用法
12歳以上
体重80kg未満:20mg錠2錠を1回内服
体重80kg以上:20mg錠4錠を1回内服
12歳未満
体重20~40kg未満:20mg錠1錠
体重40kg以上:20mg錠2錠
※20kg未満の小児は治療のみ対応。
予防効果
家庭内曝露による発症リスクを86%減少したというデータあり。
特徴
1回内服で完結し、10日間効果を持続。
イナビル®(ラニナミビル)
用法
10歳以上は2キット(10歳未満は1キット)を吸引。
予防効果
吸引から10日間インフルエンザ発症リスクを76%減少したデータあり。
特徴
1回吸入で完結し、水なしで服用可能。
注意事項
薬剤の使用はインフルエンザ曝露後48時間以内に開始する必要があります。
副作用には軽度の胃腸症状や頭痛、まれに重篤なアレルギー反応が含まれる場合があります。薬剤の安全性はある程度確認されておりますが、予防投与については、大きな副作用が発生した場合、厚生労働省の「医薬品副作用被害救済制度」の対象外になる可能性がありますので、あらかじめご了承の上、服用してください。
また、症状が無い状況での服用についても注意が必要です。例えば、受験生の場合、症状の有無によらず、受験日時に合わせて事前に服用するという使い方はやはり推奨されません。あくまでも薬剤ですので副作用のリスクも考慮する必要があり、服用は自己責任となります。
予防薬の投与に加え、以下の対策を併用することが推奨されます
ワクチン接種
インフルエンザ予防の最も効果的な方法です。感染予防のみならず、発症時の症状軽減にも効果があるとされています。
手洗い、うがい、マスク着用
基本的な感染対策です。
よくある質問Q&A
どちらもインフルエンザウイルスの増殖を抑える薬ですが、作用の仕組みと服用方法が異なります。
ゾフルーザは「ウイルスが体内で複製されるのを防ぐ」薬で、1回の内服だけで完結します。一方イナビルは「ウイルスの放出を防ぐ」吸入薬で、1回吸入するだけで効果が持続します。
どちらも高い予防・治療効果が期待できますが、飲み薬が得意な方はゾフルーザ、吸入で完結したい方はイナビルといった形で選ばれることが多いです。
ウイルスは感染直後から急速に増殖するため、早い段階で薬を使うほど効果が高まります。発症から48時間を過ぎると、すでにウイルスが体内で増えきってしまうため、薬の効果が十分に得られにくくなります。予防投与も同様に、接触から48時間以内の開始が推奨されています。
吐き気や腹痛、頭痛などの軽い胃腸症状がみられることがあります。まれに発疹やアレルギー反応などが起こる場合もありますが、ほとんどの方は問題なく服用できます。異常を感じた場合は、自己判断で中止せず、すぐに医師にご相談ください。
一部で耐性ウイルスの報告がありますが、正しく使用すれば安全性は確認されています。副作用の頻度も他の抗インフルエンザ薬と大きな違いはなく、「危険な薬」という認識は誤解です。ただし、不要な服用や頻回使用は避けることが大切です。
一般的には、服用後1〜2日で熱が下がり、症状も軽くなります。完全な回復までの期間は個人差がありますが、薬を使わない場合に比べて1日ほど早く治るとされています。重症化を防ぐ効果も期待できます。
ワクチン接種をしていても、感染の可能性を完全にゼロにすることはできません。家族内で感染者が出た場合などは、重症化リスクの高い方には予防投与を併用することがあります。医師の判断のもとで適切に使用しましょう。
予防投与は「まだ発症していない方」が対象で、感染しても発症しないように抑える目的で使用します。一方、治療投与はすでに発症している方に対して、症状を軽くしたり早く治すために使われます。目的と投与時期が大きく異なります。
多くの場合は併用できますが、服用中の薬によっては注意が必要な場合があります。特に肝臓や腎臓に負担がかかる薬を使っている方は、事前に必ず医師・薬剤師に相談してください。
一般の風邪薬(総合感冒薬)には、熱や痛みを抑える成分が含まれており、抗インフルエンザ薬と作用が重なることがあります。市販薬との併用は避け、医師から指示された薬のみを使用するのが安全です。
現時点では、人が服用を繰り返すことで効かなくなる「耐性」は確認されていませんが、ウイルス側が変異して薬の効きが悪くなる場合があります。そのため、必要な時期に必要な方が使用することが重要です。毎年のワクチン接種をあわせて行うことで、より効果的に予防できます。