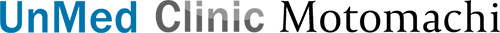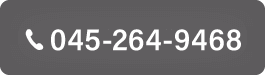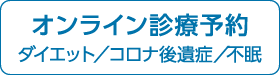YouTubeチャンネル 『Dr.高倉のUnMed TV』
【内科医が教える】機能性ディスペプシアの症状、改善、治し方について徹底解説
機能性ディスペプシアについて動画で詳しく説明しておりますのでご参照ください。
機能性ディスペプシア
 機能性ディスペプシア(FD:Functional Dyspepsia)とは、実際に逆流性食道炎や胃がんなどの器質的な病気が無いのに、食道や胃の痛みや胸やけ、胃もたれなどの症状に悩まされる機能的な病気です。そのため、血液検査や内視鏡検査、超音波検査、CT検査など、あらゆる検査をしても明らかな疾患を認めないのが特徴です。日本人の約25%は機能性ディスペプシアの症状があると報告されており、継続する胃痛によってご飯を美味しく食べられない、気持ちが滅入るなど生活の質まで低下させてしまう病気です。
機能性ディスペプシア(FD:Functional Dyspepsia)とは、実際に逆流性食道炎や胃がんなどの器質的な病気が無いのに、食道や胃の痛みや胸やけ、胃もたれなどの症状に悩まされる機能的な病気です。そのため、血液検査や内視鏡検査、超音波検査、CT検査など、あらゆる検査をしても明らかな疾患を認めないのが特徴です。日本人の約25%は機能性ディスペプシアの症状があると報告されており、継続する胃痛によってご飯を美味しく食べられない、気持ちが滅入るなど生活の質まで低下させてしまう病気です。
機能性ディスペプシアという病気は、比較的新しく確立された病名ですが、これまでの診断では、神経性胃炎や胃痙攣、胃下垂などとされてきました。
患者さん自身の痛みや苦痛の割に、検査を行っても特定の病気が見つからないため適切な対処をしてもらえず、病状が悪化してしまうケースもあるので注意が必要です。
機能性ディスペプシアの症状
機能性ディスペプシアの主な症状としては、食後の胃もたれ、早期満腹感、みぞおちの痛み、みぞおちの焼ける感じの4つの症状が見られます。その他、吐き気や嘔吐、ゲップも目立つようになります。これらの症状は大きく以下の2つに分けられます。
- 食後愁訴症候群(しょくごしゅうそしょうこうぐん)
食後の胃もたれ感、食事の途中で満腹になってしまう早期満腹感のように、食事を摂取することで不快な症状が現れるのが特徴です。 - 心窩部痛症候群(しんかぶつうしょうこうぐん)
みぞおちの痛み、みぞおちの焼ける感じといった症状が現れます。こちらは食事の摂取とは関係なく症状が見られるのが特徴です。 - みぞおちの激痛
みぞおちの激しい痛みがある場合、その原因として機能性ディスペプシアが関係していることもあります。特に内視鏡や画像検査で明確な異常が見つからないときには、このような機能性の消化管疾患が疑われることがあります。ただし、みぞおちの激痛は他の深刻な疾患が原因となっていることもあるため、注意が必要です。たとえば、胃・十二指腸潰瘍、胃がん、胆石症、膵炎、さらには狭心症などの疾患によって、みぞおちに激痛が引き起こされているケースもあります。次のような症状を伴っている場合には、機能性ディスペプシアよりも器質的疾患の可能性が高くなるため、慎重な対応が求められます。
・激痛が急に始まった
・冷や汗が出る、立ちくらみや動悸を感じる
・吐血や黒色便がある(消化管出血の兆候)
・意図しない体重の大幅な減少がある
このような症状がみられるときは、自己判断で様子を見るのではなく、速やかに医療機関を受診することが重要です。専門的な診察と検査によって正確な原因を明らかにし、適切な治療へとつなげていくことが勧められます。
機能性ディスペプシアのセルフチェック
ご自身の症状に、次のようなものが当てはまる場合には、機能性ディスペプシアの可能性があります。
- 食事をした直後に胃が重く感じる(胃もたれのような感覚がある)
- それほど多く食べていないのに、すぐにお腹がいっぱいになる(食事の途中で満腹に感じてしまう)
- 胃の上あたり(みぞおち)にキリキリとした痛みを感じることがある
- 胃のあたりが焼けるように不快に感じることがある
- 排便をしても、これらの症状が楽にならない
機能性ディスペプシアの原因
機能性ディスペプシアは、複数の要因が相互に作用して発症すると考えられています。例えば、胃の蠕動運動(ぜんどううんどう)障害や、ストレス、自律神経の乱れ、胃の知覚過敏、暴飲暴食などの生活習慣が原因とされています。
胃の蠕動運動障害
胃の蠕動運動が鈍くなり、食べたものが上手く胃の下流に流れなくなることで症状が現れます。胃の動きが鈍ると、口から入ってきた食べ物を胃で十分に受け止められず、早期膨満感や吐き気などを引き起こします。この症状を訴える患者様は比較的多くいらして、機能性ディスペプシアの患者様の約25~40%の方に認められる症状です。
さらに、胃の動きが悪くなると、胃から十二指腸に食べ物が上手く流れず、食後の胃もたれ感などを引き起こします。この症状も多くの機能性ディスペプシア患者様で認められ、約40~50%の方に見られます。
胃の知覚過敏
胃の知覚過敏といって、普段私たちの身体は食べ物をたくさん食べても胃の痛みはあまり感じませんが、胃が過敏になると、食べ物が胃に入ることでみぞおちの痛みやみぞおちの焼ける感じといった不快な症状を引き起こします。
ストレスや気分の不調
過度なストレスなどの精神的な負荷がかかると、自律神経のバランスが乱れ、それによって胃の働きが不規則になることがあると言われています。
ヘリコバクターピロリ感染症による胃の炎症
ピロリ菌と機能性ディスペプシアとの関連性は明確ではありませんが、ピロリ菌は胃炎を引き起こし、また胃がんの原因ともされています。ピロリ菌を除菌することで、胃もたれの症状は改善します。
生活習慣
機能性ディスペプシアの発症には、生活習慣が関係していることがわかってきています。たとえば、一度に多くの食事をとる(暴飲暴食)習慣や、脂っこい食事を頻繁に摂ることは、胃の動きが悪くなり、食べたものが胃に長くとどまりやすくなるため、機能性ディスペプシアの原因のひとつと考えられています。また、香辛料やカフェイン(コーヒーなど)、アルコールなどの嗜好品を摂りすぎたり、喫煙の習慣がある方は、胃酸の分泌が過剰になったり、胃がちょっとした刺激にも敏感に反応しやすくなったりすることで、症状が現れやすくなると指摘されています。さらに、慢性的な睡眠不足や疲労、不規則な生活リズムといったストレスが積み重なると、自律神経のバランスが乱れ、胃の働きにも悪影響を及ぼすため、機能性ディスペプシアを引き起こす要因になる可能性があります。
胃酸過多
胃酸が必要以上に分泌されると、胃や十二指腸の粘膜が刺激に対して過敏になりやすくなります(知覚過敏)。その結果、ちょっとした刺激でもみぞおちの痛みや胃もたれなどの不快な症状が出やすくなります。さらに、胃の動きが低下して、食べたものや胃酸がスムーズに先へ送られにくくなると、余分な胃酸が十二指腸に流れ込みやすくなり、症状がさらに悪化することもあります。
遺伝
機能性ディスペプシアは、生まれ持った体質や遺伝的な要因が関係していることもあります。たとえば、家族に同じような胃の不調がある方や、胃腸が刺激に敏感だったり、胃の動きが遅い体質の方は、少しの刺激でも症状が出やすい傾向があります。また、痛みの感じ方や胃腸の働きに関わる体質の違いが、症状の出やすさに影響している可能性があることも研究で示されています。
感染性胃腸炎
過去にウイルスや細菌による感染性胃腸炎にかかった経験がある方は、その後、機能性ディスペプシアを発症するリスクが高くなることがあると報告されています。このようなケースは「感染後機能性ディスペプシア」と呼ばれ、胃腸の炎症が治ったあとでも、胃の感覚が敏感になったり、胃の動きが乱れたりすることで症状が長引くことがあります。特に、下痢や嘔吐、腹痛を伴う急性胃腸炎のあとに、胃もたれやみぞおちの不快感などが数週間以上続く場合は、機能性ディスペプシアへの移行が疑われます。
胃の形状
胃の上部が広がった形をしている「瀑状胃(ばくじょうい)」のような構造の違いが、胃もたれなどの不快な症状と関係していることがあります。ただし、すべての人に症状が出るわけではありません。
機能性ディスペプシアの診断
まず、問診を行います。問診結果から必要に応じて検査を実施します。
上部内視鏡検査(胃カメラ)
上部内視鏡検査で、ガンや潰瘍などの器質的疾患の有無を診断します。
レントゲン、腹部超音波検査
胃以外の臓器の異常による場合があるので、何らかの疾患が隠れていないか評価します。
内視鏡検査に関しては、近隣の連携医療機関で検査を受けて頂きます。
CT検査
超音波検査では、胃や腸の動きや周囲の臓器の状態をある程度まで確認できますが、より深い位置にある臓器や、細かい構造の確認には限界があります。そのため、がん・腫瘍・炎症などの明らかな器質的疾患がないかを、さらに詳しく調べる必要があると医師が判断した場合には、CT検査を追加で行うことがあります。CT検査は、体内を輪切りのように撮影して画像を再構成することで、立体的に臓器の状態を把握できる検査です。胃や腸に加えて、膵臓・肝臓・リンパ節・血管など、腹部のさまざまな臓器を広範囲に確認することができます。機能性ディスペプシアは、内視鏡や画像検査で異常が見つからない場合に診断される疾患であるため、CT検査は他の疾患(器質的疾患)を除外する目的で行われることがあります。
機能性ディスペプシアの治療
機能性ディスペプシアと診断された場合、日常生活を健やかに送るためにも、まずは胃の痛みなどの不快な症状を速やかに取り除くことが先決です。原因となっている生活習慣の改善を見直して頂きながら、適切な薬物療法を患者様1人1人の症状と原因に応じて行っていきます。
薬物療法
- 胃酸分泌抑制薬
- 消化管運動機能促進薬
患者様の症状や原因に応じて適切な内服薬を選択していきます。治療経過を見ながら、それでも症状が改善しない場合は、抗うつ薬または抗不安薬を使用することもあります。
漢方
機能性ディスペプシアの治療では、胃酸の分泌を抑える薬や、胃の働きを助ける薬(消化管運動機能改善薬)が一般的に用いられます。ただし、これらの薬だけでは十分に症状が改善しない場合や、服用が体質に合わない場合もあります。そうしたケースでは、治療の選択肢として漢方薬を取り入れることがあります。漢方薬は、胃や腸の症状だけでなく、心身のバランスや自律神経の不調、ストレスとの関係にも目を向けて処方されるため、さまざまな症状が重なっている方や、慢性的な不調に悩む方に適している場合があります。たとえば、胃の働きを整えて食欲不振や胃もたれを改善したい方には「六君子湯(りっくんしとう)」、
みぞおちの張りや不快感、軟便などがある方には「半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)」、
ストレスが原因で胃の不快感が強く出る方には「半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)」が選ばれることがあります。当院では、西洋薬と漢方薬のそれぞれの特長を活かしながら、一人ひとりの体質や症状に合わせた治療をご提案しています。
生活習慣の改善
- 過労や睡眠不足は自律神経を乱すのでなるべく避ける
- ストレスを溜め過ぎない
- 禁酒、禁煙
- コーヒーや紅茶の飲む回数を減らすまたは薄くする
- 甘い、辛いなどの刺激の強い食べ物の摂取を減らす
- アルコールは飲み過ぎないように休肝日をつくる
- ケーキやチョコレートなどの高脂肪食や消化の悪い食事の摂取制限
- みかんなど柑橘系の摂取を減らす
よくある質問
機能性ディスペプシアを自分で改善する方法はありますか?
生活習慣を整えることで、機能性ディスペプシアの症状が緩和することがあります。以下の対策が推奨されます。
- 少量ずつよく噛んでゆっくり食べる
- 刺激物(香辛料・カフェイン・アルコール)を控える
- 十分な睡眠をとる
- 適度な運動や趣味でストレスを発散する
- 禁煙する
これらの工夫でも改善しない場合は、医療機関の受診が必要です。
機能性ディスペプシアは完治する疾患ですか?
機能性ディスペプシアは慢性的に経過する傾向があり、症状の波があることもあります。ただし、薬物療法と生活改善を継続することで、症状をコントロールし、日常生活を快適に過ごせるようになる方も多くいます。「完治」ではなく、「うまく付き合っていく」ことを目標にするのが現実的です。
機能性ディスペプシアの方が避けた方がよい食べ物はありますか?
絶対に避ける必要はありませんが、以下のような食品は胃の負担になりやすく、症状が悪化することがあります。
- 脂っこい料理(揚げ物など)
- 辛味の強い香辛料
- カフェインを多く含む飲料(コーヒー、紅茶など)
- アルコール類(特に空腹時)
- チョコレートやケーキなどの高脂肪食品
- 酸味の強い食品(柑橘類、酢の物など)
症状があるときは控え、安定しているときに少量から再開するのが望ましいとされています。
安静にしていると機能性ディスペプシアが悪化することはありますか?
身体を休めることでストレスが緩和され、症状が軽くなることがあります。一方で、過度に動かずにいると運動不足から自律神経が乱れ、胃腸の働きが低下する可能性もあるため、適度な活動と規則正しい生活リズムの維持が大切です。
胃薬を飲んでも機能性ディスペプシアが改善しないのはなぜですか?
機能性ディスペプシアは、胃酸の分泌異常だけでなく、胃の運動機能の低下や感覚過敏、自律神経の乱れなど複数の要因が関与します。そのため、一般的な胃酸を抑える薬だけでは不十分なことがあります。消化管の動きを助ける薬や、抗不安薬、漢方薬などが必要になるケースもありますので、症状が改善しない場合は医師に相談しましょう。
機能性ディスペプシアは難病に指定されていますか?
いいえ。機能性ディスペプシアは日本の「指定難病」には含まれていません。重篤な疾患ではないとされ、薬や生活の工夫によって症状のコントロールが可能であるためです。ただし、症状が長期化して生活に影響を及ぼすこともあるため、継続的な診療が必要な場合もあります。
機能性ディスペプシアはどの年代に多い疾患ですか?
機能性ディスペプシアは年齢を問わず起こり得ますが、特に20代から40代の方に多い傾向があります。ストレスや不規則な生活、食習慣の乱れなどが重なりやすい年代といえます。中高年以降の方にも発症しますが、この年代では胃がんや潰瘍などの他の疾患との区別が重要なため、内視鏡検査などを含めた精密検査が勧められます。