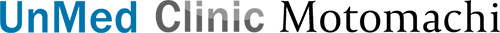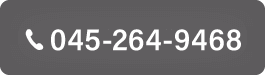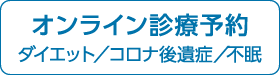みぞおちの痛み
このような胃痛・みぞおちの痛みはありますか?

- 急に痛みが起こる
- 食後に痛くなる
- 発熱や吐き気を伴う痛み
- 痛みが何日も続いている
- 痛みはそこまで強くないが、断続的に痛みが続く
- 特定の食べ物や飲み物を口にすると痛みが起こる
- 夜間、早朝など決まった時間帯に痛くなる
- 空腹時や満腹の時に痛くなる
- 強いストレスを感じると痛くなる
- 市販の鎮痛剤を服用すると痛みが起こる
上腹部の中心にあたるみぞおちに起こる痛みは、主に胃腸の異常が原因ですが、ときに胆のうや膵臓や胸部の異常によって起こることもあるため、痛みの場所以外にも痛み方や一緒に現れる症状など、きちんと把握しておくことが大切です。
みぞおちの痛みとストレスの関係
過度な精神的ストレスは自律神経が乱れやすくなり、胃酸の分泌が過剰になったり胃粘液の分泌量が減って胃や十二指腸にダメージを受けやすくなります。
夏にエアコンで冷え切った室内や冬の暖房が効いた室内と外との激しい温度差による身体的なストレスも、自律神経のバランスを崩す原因になります。
胃の粘膜が胃酸によって傷つけられることによって、胃やみぞおちのあたりに痛みが現れます。
日常生活から考えられる原因
食生活の乱れ
みぞおちの痛みは、日常の食習慣によって引き起こされることがあります。脂っこい食事や早食い・暴飲暴食は胃に負担をかけ、胃酸の分泌を促進することで、粘膜を刺激しやすくなります。また、長時間空腹の後に急に食事を摂ったり、香辛料や炭酸飲料の摂取も、胃の働きを乱して痛みの原因になることがあります。こうした習慣がある方は、まず食生活を整えることが、みぞおちの不快感の軽減につながります。
精神的なストレス
みぞおちの痛みは、食事内容だけでなく、心の緊張や精神的な負担とも大きく関係しています。たとえば、仕事上のプレッシャーや人間関係の悩み、睡眠の質の低下などによるストレスは、自律神経の働きを乱し、胃の動きや胃酸の分泌に影響を与えます。そのため、みぞおちの不快感や痛みといった症状が現れやすくなります。特に、不安や緊張を感じやすい方は、症状がなかなか治まらず、検査を受けても明らかな異常が見つからないのに胃の痛みが続く状態(機能性ディスペプシア)になることがあります。
ホルモンバランスの変動
みぞおちの痛みは、体内のホルモンの変動によって起こることもあります。特に女性では、生理周期や妊娠、更年期などに伴ってホルモンバランスが変化しやすく、それにより自律神経の働きが乱れやすくなる傾向があります。自律神経が不安定になると、胃の動きが鈍くなったり、胃酸の分泌が過剰になることで、みぞおちに不快感や痛みを感じることがあります。さらに、ホルモンの変化によってストレスに対する感受性が高まりやすくなるため、心理的な影響とあわせて症状が出やすくなることもあります。
喫煙・飲酒
みぞおちの痛みは、普段の飲酒や喫煙の習慣とも深く関わっています。アルコールを摂取すると、胃酸の分泌が促進され、胃の粘膜に刺激を与えるため、炎症を起こしやすくなります。とくに、空腹時にお酒を飲んだり、一度に多量のアルコールを摂取すると、胃への負担が大きくなり、胃の不快感やみぞおちの痛みを引き起こす原因になります。また、たばこに含まれる成分には胃粘膜の血流を低下させたり、防御機能を弱めたりする作用があるため、胃酸によるダメージを受けやすくなります。これにより、慢性的な胃の違和感や、胃炎・胃潰瘍のリスクが高まることもあります。
睡眠不足
みぞおちの痛みは、睡眠不足や生活リズムの乱れが原因となることもあります。眠りが浅かったり、十分な睡眠時間を確保できない状態が続くと、自律神経の調整機能が乱れやすくなり、胃の働きや胃酸の分泌が不安定になります。その結果、胃に負担がかかり、みぞおちに違和感や痛みを感じることがあるのです。さらに、睡眠が不足すると、心身の疲労が蓄積しやすくなり、ストレスや緊張感が強まることで胃の症状が悪化しやすくなることもあります。
カフェインの摂取(コーヒー・エナジードリンク)
みぞおちの痛みは、普段から摂っているカフェイン入りの飲み物が関係していることもあります。たとえば、コーヒーや紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、胃酸の分泌を活発にする作用があり、これによって胃の粘膜が刺激を受けやすくなると考えられています。特に、空腹の状態でカフェインを摂取すると胃にかかる負担が大きくなり、みぞおちに違和感や痛みを感じる原因になることがあります。さらに、カフェインには神経を興奮させる働きもあるため、ストレスや睡眠不足などが重なると自律神経のバランスが乱れやすくなり、胃の不調が悪化する可能性があります。
運動不足
みぞおちの痛みは、運動不足が影響している場合もあります。日常的に体を動かす習慣が少ないと、胃や腸の動きが鈍りやすくなり、消化がスムーズに進まなくなることで、胃もたれやみぞおちの違和感が生じることがあります。特に、座りっぱなしの時間が長い生活や、運動をほとんど行わない状態が続くと、胃の動きが低下し、食後に膨満感や痛みを感じやすくなります。さらに、身体を動かさないことが精神的ストレスの蓄積や睡眠の質の低下につながることもあり、こうした要素が重なると自律神経の働きが乱れ、みぞおちの痛みが悪化する可能性があります。
胃やみぞおちの痛みの原因となる疾患
逆流性食道炎
加齢などが原因で胃液が逆流を繰り返すと食道の粘膜が傷ついて、炎症が起こります。
激痛とまではいきませんが、胸やけや呑酸、胸のあたりの痛み、飲み込みにくさ、げっぷが出やすくなるなどの症状が現れます。夜間や空腹時に症状がみられます。また、体を横にしている状態の時に症状が起こりやすい傾向があります。
機能性ディスペプシア
慢性的なみぞおちの痛みや胸やけ、胃の痛み、げっぷなどの症状があるにも関わらず、検査などで逆流性食道炎や胃がんなどの病気がみられない場合は、機能性ディスペプシアかもしれません。
機能性ディスペプシアは、症状がでていても検査では明確な疾患が認められないという特徴があります。
急性胃炎
暴飲暴食、飲酒、過度なストレス、食中毒やピロリ菌の感染など様々な原因で胃の粘膜がただれると、みぞおちがキリキリと痛むことがあります。みぞおちの痛みの他に、吐き気や下痢を伴うこともあります。さらにひどい場合は嘔吐や吐血、下血を起こすこともあります。通常、2〜3日安静に過ごせば症状は改善していきます。
胃潰瘍・十二指腸潰瘍
ピロリ菌の感染やストレス、非ステロイド系消炎鎮痛剤やステロイド薬の服用などが原因で、胃液の消化作用により胃や十二指腸の粘膜に潰瘍ができます。みぞおちの周辺にズキズキと重苦しい痛みが起こるのが特徴です。また、げっぷや胸やけが伴うこともあります。
胃潰瘍は、食べたものが胃に入ると潰瘍を刺激するので食事中~食後に痛みが現れます。十二指腸潰瘍は、空腹時に痛みが現れます。
慢性胃炎
慢性胃炎の主な原因は、ピロリ菌です。ピロリ菌に感染して長期にわたり放置していると炎症が胃全体に広がっていきます。繰り返しもしくは持続的に起こるみぞおちの痛みや胸やけ、胃もたれ、吐き気、嘔吐、食欲不振、膨満感など様々な症状が現れます。
十二指腸炎
ピロリ菌やストレス、飲酒、薬剤の副作用など様々な要因で十二指腸の粘膜が傷つき炎症が起こっている状態です。慢性的な炎症によって、みぞおちや背中の痛みなどの症状が起こります。まれに吐き気や不快感などの症状を伴うことがあります。
食中毒
食中毒は、食品に含まれる細菌・ウイルス・毒素などが原因で起こる体調不良です。主な原因には以下のようなものがあります。
- カンピロバクター(加熱不足の鶏肉・汚染水)
- O-157などの腸管出血性大腸菌(生肉・汚染野菜)
- サルモネラ菌(生卵・加熱不十分な肉)
- 腸炎ビブリオ(生の魚介類)
- 黄色ブドウ球菌(傷口などから食品へ)
- ノロウイルス(二枚貝・人からの感染)
また、フグ毒、毒キノコ、ジャガイモの芽などによる自然毒による食中毒もあります。これらの食中毒では、食後数時間以内にみぞおちの強い痛みが起こり、吐き気・嘔吐・下痢・発熱などの症状を伴います。重症化することもあるため、異変を感じた場合は早めに医療機関を受診しましょう。
胃アニサキス症
胃アニサキス症は、アニサキスという寄生虫が生または加熱不十分な魚介類(サバ、アジ、イカ、サケなど)を食べることで胃の粘膜に入り込み、痛みを引き起こす疾患です。食後2~6時間以内に、みぞおちの激しい痛みや吐き気、嘔吐などの症状が急に現れるのが特徴です。診断後は、胃カメラでアニサキスを摘出することで症状が改善します。予防には、魚介類を冷凍(-20℃以下で24時間以上)または十分に加熱してから食べることが重要です。
胆石症
胆石は、肝臓で作られた胆汁が石のように固まったものです。胆のうや胆のう管、総胆管などの胆汁の通り道となる場所に胆石ができると激しいみぞおちの痛みが起こります。
特徴として右肩に響くような痛みがあり、また発熱や嘔吐を伴うこともあります。胆汁の流れが悪くなっていくと、顔が黄色くなったり尿の色が濃くなる黄疸の症状が現れます。
発作が起こると血流が低下してショック症状により顔が真っ青になる恐れがあります。中年以降の肥満の方は、特に発症リスクが高いため注意が必要です。
胆のう炎
胆のう管に結石が詰まると胆のう壁が傷ついて炎症が起こります。
食後に右上腹部や背中に激しい痛みが現れるのが特徴です。また、吐き気や嘔吐、発熱などの症状を伴う場合があります。発熱している場合は、緊急の外科手術が必要となることがあります。
急性膵炎
急性膵炎は、膵臓から分泌される消化酵素が膵臓内で異常に活性化し、自分の膵臓を傷つけて炎症を起こす疾患です。主な原因は過度の飲酒と胆石による胆管の詰まりです。最初は胃のあたりの軽い痛みから始まりますが、次第にみぞおちを中心に鋭い痛みが起こり、腹部全体や背中にまで広がる強い痛みに変わることがあります。痛みに伴って筋肉痛のような違和感を覚えることもあります。急性膵炎は重症化すると命にかかわる恐れがあるため、強い痛みや異常を感じた場合は、早めに医療機関を受診することが大切です。
急性胆管炎
急性胆管炎は、胆石や腫瘍によって胆管(胆汁の通り道)が塞がれ、そこに細菌が感染して炎症を起こす疾患です。胆汁の流れが滞ることで細菌が増殖し、全身に症状が現れます。主な症状は、みぞおちや右上腹部の強い痛み、吐き気・嘔吐・発熱・寒気・黄疸(皮膚や目の黄ばみ)などです。症状は急速に悪化することがあり、重症化すると敗血症を引き起こす可能性もあります。早期の診断と治療が必要です。
急性虫垂炎
急性虫垂炎は、虫垂に細菌が感染し、炎症を起こす疾患です。初期には胃やみぞおち周辺に痛みを感じることがあり、吐き気や嘔吐を伴う場合もあります。痛みは発症から数時間〜半日かけて、右下腹部へ移動するのが特徴です。この移動する痛みは、急性虫垂炎を見分ける手がかりになります。放置すると虫垂が破れて腹膜炎を起こすこともあるため、早めの受診と治療が必要です。
心筋梗塞
心筋梗塞は、心臓の血管(冠動脈)が血栓で詰まり、心筋への血流が途絶えて壊死を起こす疾患です。重症化すると命にかかわることがあります。発作時には、胸の中央やみぞおちに激しい痛みが起こり、冷や汗や呼吸困難を伴うのが特徴です。筋肉痛のような圧迫感や締めつけられる感覚として現れることもあり、痛みが背中や左腕、顎などに広がることもあります。主な原因は動脈硬化で、高血圧・脂質異常症・糖尿病・喫煙・肥満・運動不足・食生活の乱れなどが重なると、発症リスクが高まります。
胃がん
肺がんや大腸がんに次いで死亡数の多い胃がんは、初期のころは自覚症状が乏しく、病気が進行していくとみぞおちの痛みの症状の他に胸の不快感や吐き気、食欲不振などを伴うことがあります。
食道がん
がん細胞が食道に増殖すると、食べ物を飲み込むときに胸や背中が強く痛む特徴があります。
食道は、初期のころは自覚症状が乏しく、進行していくと咳やのどの痛み、声枯れ、急な体重減少、げっぷが増えるなどの症状などが現れます。
みぞおちの痛みの対処方法
市販薬の使用
みぞおちの痛みに加えて胃痛・胃もたれ・胸やけがある場合、市販薬を服用することで一時的に症状がやわらぐことがあります。たとえば、胃酸が原因と思われるときには、制酸薬やH2ブロッカー、PPI(胃酸の分泌を抑える薬)を選ぶとよいでしょう。食後の膨満感や胃の動きの悪さを感じる場合は、消化酵素や胃の運動を助ける薬が選択肢になります。また、ストレスや自律神経の乱れが関係していると考えられる場合には、六君子湯(りっくんしとう)などの漢方薬を試してみるのも一つの方法です。ただし、症状が繰り返し現れる、数日以上続く、あるいは強い痛みを感じる場合には、市販薬だけで対処せず、早めに医療機関を受診しましょう。
消化の良い食事・一時的な絶食
みぞおちの痛みがあり、暴飲暴食をしてしまった心当たりがある場合は、胃腸への負担を減らすために消化の良い食事を選ぶことが大切です。症状が強いときには、半日から1日程度、食事を控えて胃を休ませる「一時的な絶食」が有効な場合もあります。ただし、絶食中も水分は必要です。冷たい飲み物や一度に大量に飲むのは避け、常温の水や白湯を少しずつ摂るようにしましょう。痛みが和らいできたら、おかゆやスープなどから少しずつ食事を再開し、体調に応じて通常の食事へと戻していくことが望ましいです。症状がなかなか改善しない場合や、繰り返すようであれば、早めに医療機関を受診してください。
上半身をやや高くし、右側を下にして横になる
みぞおちの痛みがあり、胃酸の逆流が関係している場合は、就寝時に上半身をやや高くして横になることで、症状がやわらぐことがあります。枕やクッションを使って、頭から胸にかけて少し傾斜をつけると、胃の内容物が食道へ逆流しにくくなります。さらに、横になる際は右側を下にすることで、胃の出口が下向きとなり、逆流を防ぎやすくなります。ただし、これらは就寝時の姿勢に関する工夫であり、食後すぐに横になることは避けましょう。少なくとも食後2時間は、立つか座って過ごすようにしてください。
みぞおちの痛みに対する検査
みぞおちの痛みは、胃・食道・膵臓・胆のう・心臓などの異常が原因となることがあります。原因を特定するために、問診の内容をもとに以下のような検査が行われます。
- 血液検査(炎症や感染、膵臓・肝臓・心筋の異常を確認)
- 腹部エコー(超音波検査)(胆石、胆のう炎、膵臓や肝臓の腫れを調べる)
- 胃カメラ(上部内視鏡)(胃潰瘍、逆流性食道炎、胃がんの有無を直接観察)
- CT検査(膵炎や胆管閉塞、腫瘍などを詳しく確認)
- 心電図・心臓の血液検査(狭心症や心筋梗塞の有無を調べる)
これらの検査により、痛みの原因を明確にし、適切な治療につなげることができます。痛みが強い、繰り返す、吐き気・発熱・黄疸などを伴うときは、早めに医療機関を受診しましょう。
みぞおちの痛みに対する予防法・治療方法
規則正しい食生活
食べ過ぎ飲み過ぎはもちろん、朝食を抜いたり遅い時間に食事を摂ったりすることも、胃腸に負担をかけます。3食きちんと規則正しい時間に食べて、腹八分目に留めるようにすることが大切です。特に、寝る前の脂ものは控えましょう。また、アルコールは適量ならば問題ありませんので、過度の飲酒は控えましょう。
口にする食べ物の鮮度や生水に注意する
気温も湿度も高く、食あたりが増える6〜9月頃の時期は、食品の鮮度を冷蔵庫で保ちましょう。さらに、まな板や包丁などの調理器具を清潔にする配慮も欠かせません。また気をつけたいのは海外旅行中の飲料です。特にアジア方面への渡航では生水は避け、屋台などでの果汁飲料や氷にも注意が必要です。
ピロリ菌を除菌する
病院でピロリ菌検査を受けると、感染の有無が分かります。いくつか検査方法がありますが、呼気検査や血液中のピロリ菌抗体検査など、どれも簡単に調べることが出来ます。また、約90%程度の患者さんは、処方薬を1週間服用することで痛みもなくピロリ菌を除去すること可能です。ピロリ菌の除去は、慢性胃炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍、さらには胃がんを予防する効果が認められています。
よくある質問
みぞおちが痛むとき、受診するタイミングはいつですか?
みぞおちの痛みが数日以上続く、または繰り返し起こる場合には、なるべく早く医療機関を受診することが推奨されます。特に、強い痛みや発熱・吐き気・黄疸などの症状を伴うときは、消化器や肝胆膵の疾患が疑われます。また、突然の激しい痛みに加えて冷や汗、息苦しさ、肩や背中に響く痛みがある場合は、心筋梗塞などの緊急性の高い疾患の可能性があるため、すぐに救急受診が必要です。
みぞおちの痛みで受診すべき診療科は?
みぞおちの痛みがある場合は、まず消化器内科の受診が適しています。胃・十二指腸・胆のう・膵臓などの異常が原因となるケースが多いためです。症状や診察結果によっては、一般内科や、心臓疾患が疑われる場合は循環器内科、外科的な処置が必要な場合は外科に紹介されることもあります。
みぞおちの位置と、その周辺にある臓器を教えてください
「みぞおち」は、胸骨の下から腹部にかけての上腹部中央(心窩部)を指します。この部位の周囲には、胃・十二指腸・膵臓・胆のう・肝臓・横隔膜が位置し、さらに心臓も近接しているため、関連した痛みとして感じることもあります。
胸の中央が痛くなる原因は何ですか?
胸の中心部に痛みを感じるときは、逆流性食道炎や心臓疾患(狭心症・心筋梗塞)などが考えられます。とくに、圧迫されるような痛み、冷や汗、息苦しさを伴う場合は、循環器疾患の可能性があるため、ただちに受診しましょう。一方、げっぷや胸やけがある場合は、食道や胃の異常によることが多いです。
みぞおちが締めつけられるように痛むのは胃の異常ですか?
締めつけられるようなみぞおちの痛みは、胃炎、胃潰瘍、または機能性ディスペプシアといった胃のトラブルで見られることがあります。ただし、狭心症や心筋梗塞などの心疾患でも類似の症状が現れるため、痛みが強い場合や呼吸困難・冷や汗を伴うときは、早急に受診してください。
胃の調子が悪くて背中まで痛むのは、ストレスが原因でしょうか?
精神的ストレスが影響して自律神経が乱れ、胃の働きが低下すると、みぞおちや背中に不快感を覚えることがあります。ただし、十二指腸潰瘍や膵炎でもみぞおちから背中にかけて痛みが放散するため、長引く症状がある場合は専門的な検査が必要です。
みぞおちの痛みと便秘には関係がありますか?
便秘によって腸内にガスがたまると、腹圧が上がり、みぞおち周辺に痛みや違和感が出ることがあります。また、排便が滞ることで胃の働きも影響を受けやすくなります。生活習慣の改善や排便リズムの調整によって症状が軽減するケースも少なくありません。
新型コロナウイルス感染症で、みぞおちが痛むことはありますか?
新型コロナウイルス感染症では、消化器症状(胃痛・吐き気・下痢など)がみられることがあります。特にオミクロン株以降、消化器に関連する訴えが増加しています。持続的なみぞおちの痛みがある場合には、感染症の可能性も視野に入れて、検査を検討することが望ましいです。
みぞおちが痛むときに水を飲むと楽になるのはなぜ?
軽い胃酸の過剰分泌が原因の場合、水分を摂ることで胃酸を薄めたり中和したりする効果があり、痛みがやわらぐことがあります。ただし、根本的な解決にはならないため、症状が繰り返される場合は、医療機関での検査を受けることが重要です。
食あたりと食中毒の違いは何ですか?
「食あたり」は日常的な表現ですが、「食中毒」は医師によって診断される感染性の疾患です。細菌やウイルス、自然毒などが原因で、みぞおちの痛み、下痢、嘔吐、発熱などの急性症状が現れます。重症化のリスクもあるため、症状が強い場合は速やかに医療機関を受診してください。