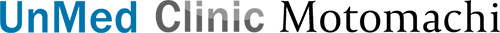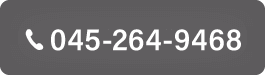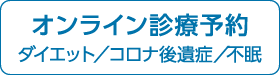YouTubeチャンネル 『Dr.高倉のUnMed TV』
朝のお腹のトラブル(腹痛、下痢)は過敏性腸症候群かも?下痢型、便秘型、ガス型など治療方法(治し方)を徹底解説
過敏性腸症候群について動画で詳しく説明しておりますのでご参照ください。
過敏性腸症候群(IBS)
 腹痛や下痢、便秘など消化器系の不快な症状が幾つかありますが、内視鏡検査や血液検査では明らかな異常が無く、消化器内科専門医でないと正確な診断が難しいとされる病気です。原因もはっきりと限定することができず、多くはストレス、食生活、生活習慣が関わっていると指摘されています。腸の機能が十分に働いていない状態には違いありませんが、緊張やストレスなどをきっかけに腹痛などの症状を引き起こします。ストレスは自律神経のバランスを崩してしまい、腸の機能をうまくコントロールできなくしてしまいます。
腹痛や下痢、便秘など消化器系の不快な症状が幾つかありますが、内視鏡検査や血液検査では明らかな異常が無く、消化器内科専門医でないと正確な診断が難しいとされる病気です。原因もはっきりと限定することができず、多くはストレス、食生活、生活習慣が関わっていると指摘されています。腸の機能が十分に働いていない状態には違いありませんが、緊張やストレスなどをきっかけに腹痛などの症状を引き起こします。ストレスは自律神経のバランスを崩してしまい、腸の機能をうまくコントロールできなくしてしまいます。
過敏性腸症候群の症状
過敏性腸症候群の主な症状は、腹痛や下痢、便秘、そして腹部膨満感などです。症状は人それぞれですが、最も多いのは激しい腹痛と強い下痢、排便後に症状が楽になるというものです。食事やストレスの影響で症状を引き起こしやすく、逆に眠っているときには症状が現れることはありません。
過敏性腸症候群のタイプ別は以下の通りです。
下痢型
突然の激しい腹痛と水のような下痢があり、排便後に楽になるという症状です。突然強い症状を引き起こすので、電車利用などの通勤や通学が不安になる、それがさらにストレスになって症状を引き起こしやすくするという負のスパイラルに陥りやすいです。こうした激しい下痢症状を1日に何度も繰り返すことがあります。
便秘型
排便時の強い腹痛があるにも関わらず、便がなかなか出ないといった便秘の症状があります。便の性状は、ウサギの糞のように小さくて硬い、コロコロした便です。排便した後もスッキリせず、残便感があります。硬い便を無理に出そうと、強くいきむ癖がついてしまい、イボ痔や切れ痔になりやすいので注意が必要です。
混合型
下痢と便秘を繰り返すタイプです。激しい腹痛を伴うため苦痛を強いられます。
分類不能型
お腹が張って苦しい膨満感やお腹がグルグルと鳴る、無意識にオナラが出てしまうなどの不快な症状が現れます。人目が気になったり、学校や職場の静かな場所では緊張や不安を感じるため、余計に悪化させやすくなります。
ガス型IBSとは?
ガス型IBSとは、腸の働きに異常が生じることで腸内にガスがたまりやすくなるタイプの過敏性腸症候群を指します。医学的に正式な分類ではないものの、おならやお腹の張りといったガス症状が中心の過敏性腸症候群を「ガス型」と呼ぶことがあります。このタイプでは、腸の動きが過剰になったり、ガスの排出がうまくいかなかったりすることで腸内にガスが蓄積しやすくなり、以下のような症状があらわれます。
- おならの回数が増える
- ガスを我慢できずに困る
- お腹の張り(腹部膨満感)が強い
- 腸が鳴る音(腹鳴)が気になる
- 腹痛や不快感を伴う場合もある
これらのガスに関する症状は、特定の食事(とくに高FODMAP食品)、精神的なストレス、自律神経の乱れなどが関与して悪化することがあると考えられています。ガス型IBSでは、人前でのおならや腹鳴に対する強い不安が、さらなるストレスを引き起こすという悪循環に陥るケースもあります。
過敏性腸症候群のセルフチェック
以下の項目について、「はい」または「いいえ」でお答えください。
【1】最近3か月の間に、月に1回以上の頻度で、お腹の痛みや不快感が繰り返し起こっていますか?
【2】その腹痛や不快感は、次のいずれかに該当しますか?
- 排便すると症状がやわらぐ
- 排便の回数が増えたり減ったりするときに、症状が出る
- 便の硬さや柔らかさがいつもと違うときに、腹痛や不快感が出る
【3】以下のような症状が見られますか?
- 突発的な下痢が続き、急にトイレへ行きたくなることがある
- 便秘がちで排便回数が少ない
- 下痢と便秘が交互に繰り返される
- お腹が張る感じやガスがたまりやすいと感じる
- 排便後もすっきりした感覚が得られない
以上のセルフチェックで【1】の問いに「はい」、かつ【2】のいずれかに「はい」が該当する場合は、過敏性腸症候群(IBS)の可能性が考えられます。さらに【3】のような症状が継続している場合も過敏性腸症候群に見られる特徴とされています。ただし、これはあくまで自己評価の目安であり、最終的な診断には医師による精査が必要です。とくに、体重減少や血便、発熱、40歳以降に初めて出現した症状、夜間の腹痛や下痢がある場合は、過敏性腸症候群以外の重大な疾患の可能性もあるため、速やかに医療機関を受診することが重要です。
ストレスと過敏性腸症候群
緊張やストレスなど精神的な原因がきっかけとなり症状が現れるため、日常生活の中でも支障をきたす場面が多く、過度な緊張状態が強いられることにより症状が起こりやすくなるといった悪循環に陥りやすい病気です。いつ便意を催すか分からない不安感、トイレが気になって外出するのが怖くなるなどの悪影響があります。
突然の腹痛と強い下痢が生じる「下痢型」では、通勤や通学、会議や面接、授業、テストなど日常の静かなシーンや緊張感のある空間では、症状が起こりやすく、それを予測できることがさらなるストレスになって、症状悪化につながっています。
適切な治療を受けることで改善を図ることができるので、まずはお気軽に当院を受診して下さい。
子どもの過敏性腸症候群
過敏性腸症候群は、大人だけでなく小学生から高校生までの子どもにも見られる疾患です。腸に明らかな異常がないにもかかわらず、腹痛や便通の乱れが慢性的に続くのが特徴です。朝になると「お腹が痛い」と訴えて登校を嫌がり、トイレに行くと症状が少し落ち着くものの、検査では異常が見つからないというケースでは、この疾患が疑われます。原因としては、学校でのストレスや生活リズムの乱れなどが関係しており、自律神経の働きの乱れや腸の過敏さが影響していると考えられています。命にかかわることはありませんが、学校生活や日常に支障をきたすことがあるため、早めの対処が大切です。生活習慣や食事の見直しに加え、整腸剤や漢方薬、心理的なサポートなどを組み合わせた対応が効果的です。「仮病ではないか」と疑われやすいこともありますが、過敏性腸症候群はれっきとした疾患です。子どもが何度も「お腹が痛い」と訴える場合は、身体だけでなく心の状態にも目を向け、小児科や消化器内科に相談することをおすすめします。
過敏性腸症候群の原因
過敏性腸症候群の原因は、明確には分かっていませんが、ストレスや緊張などの心因的原因と、食べ物、粘膜の炎症、腸内細菌叢、遺伝などが腸機能障害を引き起こすとされています。腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)は自律神経によってコントロールされているので、緊張や不安などのストレスが発症を誘発し、その他、睡眠不足や過労、不規則な食生活なども影響を及ぼしています。
過敏性腸症候群の診断
正確な診断と適切な治療を行うために、まずは丁寧な問診を実施しています。問診では、症状が起こり始めた時期や現在の症状、病状の推移、発症頻度、発症時の状況や便の状態、排便回数、症状が出現するきっかけとなる状況、食生活をはじめとする生活習慣などを伺います。その上で、他の疾患が見られず、「Rome III基準」という診断基準に当てはまる場合に「過敏性腸症候群」と診断されます。
大腸内視鏡検査が必要と判断した場合は、近隣の連携医療機関で検査を受けて頂きます。
Rome III基準とは
過去3カ月間の症状をチェックし、月に3日以上の腹痛や腹部の不快感が繰り返し起こっていて、かつ下記の条件のうち2つ以上に当てはまると医師が判断した場合、過敏性腸症候群と診断されます。
- 排便により症状が軽快する
- 症状とともに排便回数が変化する
- 症状とともに便の形状が変化する
腸内フローラ検査
当院では、サイキンソー社のMykinso(マイキンソー)という腸内フローラ検査を導入しております。過敏性腸症候群の患者様には、御自身の腸内環境を正確に把握することで、今後の適切な対応策がより具体的に導き出せる可能性が高くなるため、是非一度、この検査を受けて頂くことをお勧めしています。
過敏性腸症候群の治療
過敏性腸症候群は、症状が同じようでも原因は人それぞれ違います。当院では、過敏性腸症候群の治療経験豊富な医師による丁寧な診察で、1人1人の患者様に合った診断をすることで、最適な治療法を提供しています。適切な治療薬で辛い症状を緩和し、食事や運動、睡眠などの生活習慣をそれぞれ改善させながら、ストレスや緊張の影響を出来る限り受けないようトータルサポートし、根本的な治療と再発防止を図ります。
薬物療法
症状改善のために、消化管の蠕動運動機能改善、便の水分バランス調整などの薬剤を用います。突然の腹痛と水のような激しい下痢が起こるタイプでは、予兆を感じた時に服用できる薬剤を用います。
以前からある便の水分調整をする高分子重合体、下痢改善のためのセロトニン受容体(5-HT3受容体)拮抗薬、割と最近発売された便秘改善の粘膜上皮機能変容薬、腹痛解消の抗コリン薬、更には乳酸菌や酪酸菌などのプロバイオティクス等、患者様の症状や状態、ライフスタイルに合った、きめ細かい治療を行っていきます。
漢方薬
過敏性腸症候群の治療では、腸の動きを整える薬や整腸剤、必要に応じて抗不安薬などが使われます。ただし、これらの薬だけでは効果が不十分だったり、副作用が気になる方もいます。そうした場合には、漢方薬を併用することがあります。漢方薬は、腸の症状だけでなく、ストレスや自律神経の乱れなど全身のバランスも考慮して処方されます。たとえば、腹痛や下痢が続く方には「桂枝加芍薬湯(けいしかしゃくやくとう)」、胃の不快感や軟便がある方には「半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)」、お腹の冷えが気になる方には「大建中湯(だいけんちゅうとう)」、ストレスが強い方には「加味逍遙散(かみしょうようさん)」などが使われることがあります。当院では、西洋薬と漢方薬の特性を活かし、症状や体質に合わせた治療を提案しています。お腹の不調が長引いている方は、お気軽にご相談ください。
低FODMAP食事療法
低FODMAP食とは、過敏性腸症候群(IBS)の症状緩和を目的とした食事療法のひとつです。FODMAPは「Fermentable(発酵性)」「Oligosaccharides(オリゴ糖)」「Disaccharides(二糖類)」「Monosaccharides(単糖類)」「Polyols(糖アルコール)」の頭文字を取った略称です。これらの糖質は、小腸での吸収が不完全で、大腸に届いた後に発酵しやすいという性質があります。そのため、これらを多く含む食品(高FODMAP食品)を摂取すると、過敏性腸症候群の方ではガスの発生や腸管内の水分増加を引き起こし、腹痛や下痢、便秘といった症状が悪化する場合があります。この食事法では、まず最初に高FODMAP食品の摂取をおよそ2〜6週間の期間で制限し、症状の変化を観察します。改善が見られた際には、制限していた食品を一つずつ再び取り入れ、自分にとって問題となる食品を特定していきます。このような段階的な手法により、個々の体質に合った食事パターンを見つけることが可能です。すべての方に効果があるとは限りませんが、薬のみでは十分な改善が得られない場合の補助的アプローチとして注目されています。ただし、必要以上の食事制限は栄養の偏りを招く可能性があるため、実施にあたっては医師や管理栄養士と相談しながら進めることが重要です。過敏性腸症候群の症状が長引いている方は、食事内容の見直しを選択肢の一つとして考えてみるとよいでしょう。
| 低FODMAP食(控えなくてよいもの) | 高FODMAP食(控えめにしたいもの) |
|---|---|
| 米、玄米、十割蕎麦、ビーフン、フォー | パン、パスタ、うどん、ラーメンなどの小麦粉製品 |
| 卵、牛肉、鶏肉、豚肉、魚 | ソーセージ |
| トマト、ホウレンソウ、カボチャ、ダイコン、ジャガイモなどの野菜 | たまねぎ、アスパラガス、長ネギ、ニラ、サツマイモなどの野菜 |
| 木綿豆腐 | 大豆、納豆、豆乳 |
| メープルシロップ | はちみつ |
| バター、マーガリン | 牛乳、ヨーグルト |
| 緑茶、紅茶 | チョコレート、アイスクリーム、ウーロン茶 |
生活習慣の改善
食事編
- 3食を毎回同じ時間帯に取るようにする
- 暴飲暴食をしない
- 毎回食べ過ぎないように気を付ける
- 栄養バランスを考えた食事をする
- 十分な食物繊維と水分摂取を心がける
- 香辛料やカフェインなどの刺激物を避ける
- 飲酒量を減らす、または飲まない休肝日を設ける
生活編
- 適度な運動を毎日行う
- 十分な睡眠と休養を取る
- リラックスできる空間と時間を作る
- ストレス解消を心がける
クリニックへご相談下さい。
過敏性腸症候群は、その症状も原因も、発症するきっかけも人それぞれ異なります。よって、1人1人丁寧に診断し、適切な治療を行う必要があり、いわゆるオーダーメイドの治療が必要な疾患です。患者様の生活習慣やストレスや緊張の原因を正確に把握し、症状に対してより適切なアプローチ方法を見つけなければなりません。
当院では、丁寧な診察で適切な治療を提供しています。万が一、症状が改善しない、または悪化した場合でも、信頼できる大学病院や近隣病院との連携を取っているので安心して受診して下さい。まずは、1人で抱え込まずに気軽に当院にご相談下さい。
よくある質問
高齢の方も過敏性腸症候群になりますか?
過敏性腸症候群(IBS)は、主に20~40代の若年から中年層に多く見られますが、高齢の方でも発症することがあります。ただし、高齢で初めて腹痛や便通異常(下痢・便秘など)が現れた場合には、過敏性腸症候群以外の重大な疾患(大腸がんや炎症性腸疾患など)が隠れている可能性もあるため、自己判断せず、医師の診察を受けて必要な検査を行うことが重要です。
過敏性腸症候群は指定難病に含まれていますか?
過敏性腸症候群(IBS)は、厚生労働省の定める指定難病には含まれていません。命に直接関わる疾患ではありませんが、慢性的な症状が続くことで生活の質(QOL)を大きく損なうケースがあり、個人によっては日常生活に大きな影響を及ぼします。ただし、治療や生活習慣の見直しによって症状の緩和が期待できるため、適切な対応を行うことが大切です。
過敏性腸症候群の方はヨーグルトを避けた方がいいですか?
ヨーグルトには腸内環境を整える働きが期待されますが、過敏性腸症候群の方の中には、摂取することでかえって症状が悪化する場合があります。特に乳糖不耐症の方では、ヨーグルトに含まれる乳糖が消化されずに腸内で発酵し、ガスの発生や腹部膨満感、下痢などを引き起こすことがあります。自分の体質や症状に合わせて、乳糖を含まない発酵乳を選ぶなどの工夫が必要です。
過敏性腸症候群の症状があるときは病院にかかるべきですか?
はい。腹痛や下痢・便秘などの症状が長く続いている場合や、生活に支障が出ている場合には、医療機関での診察を受けることが望ましいです。過敏性腸症候群と似た症状を示す疾患として、大腸がんや潰瘍性大腸炎なども考えられるため、症状だけで自己判断せず、専門の医師による評価を受けることが大切です。とくに、血便・体重減少・発熱・夜間の腹痛や下痢などがあるときは、早めの受診をおすすめします。
お腹が鳴ったあとに下痢になるのはなぜですか?
腸が過敏な状態にあると、ちょっとした刺激で腸の動きが活発になりやすくなります。その結果、ガスが溜まりやすくなり、腹鳴(お腹がグルグル鳴る音)が生じ、下痢を伴うことがあります。こうした反応は、ストレスや不規則な食生活などによって自律神経の働きが乱れ、腸の運動がうまく調整できなくなることが関係しています。特に、ガス型や下痢型の過敏性腸症候群に多く見られる特徴です。
過敏性腸症候群は自然に治ることもありますか?
症状が一時的に落ち着くことはありますが、自然に完全に治ることは少なく、再び症状が現れるケースが多く見られます。放置しておくと慢性化する可能性があるため、適切な治療と生活習慣の見直しを行うことが大切です。とくにストレス管理や食事・睡眠・運動などの改善が、再発の予防に役立ちます。
過敏性腸症候群は何度も繰り返すものですか?
はい。過敏性腸症候群は再発しやすい疾患のひとつで、症状が落ち着いても再び悪化することがあります。特に精神的なストレスや食生活の乱れ、過労、睡眠不足などが引き金になる場合が多く、長期的な対策が求められます。症状のない時期でも、日々の生活を整えることが再発予防につながります。
過敏性腸症候群があると大腸がんのリスクが高まるのでしょうか?
過敏性腸症候群(IBS)そのものが大腸がんの発症リスクを高めるという証拠はありません。ただし、過敏性腸症候群と似た症状がみられる疾患には大腸がんや炎症性腸疾患などがあり、特に40歳以降に新たに腹痛や下痢などの症状が出現した場合は注意が必要です。安全のためにも、症状に異変を感じたときは医師に相談し、必要に応じて検査を受けることをおすすめします。