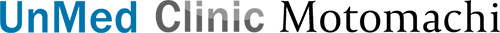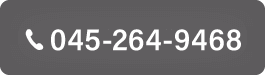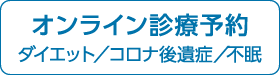吐き気の原因
 日常生活において、「吐き気」を感じることはよくあることで、暴飲暴食や過度の緊張などの場面ではそれほど珍しいことではありません。
日常生活において、「吐き気」を感じることはよくあることで、暴飲暴食や過度の緊張などの場面ではそれほど珍しいことではありません。
しかし、吐き気が起こる頻度が高かったり、継続する場合や、実際に吐いてしまう場合は、何らかの病気を疑う必要があるので、早めに医療機関を受診して下さい。
吐き気の疾患以外の原因
食生活
脂っこいものや甘いものの摂りすぎ、早食いや過食といった偏った食生活は、吐き気の原因になることがあります。特に、食後に胃の不快感やむかつきを感じる場合は、食べた内容や食べ方が関係している可能性があります。また、空腹の時間が長すぎることに加え、冷たい飲み物、香辛料やカフェインを多く含む飲食物など、刺激の強いものを摂りすぎることでも、吐き気が起こることがあります。このような場合は、少量ずつゆっくり食べることや、胃にやさしい食材を選ぶなど、食生活を見直すことで症状の改善が期待できます。
精神的なストレス
緊張や不安、強いストレスが続くと、自律神経の乱れから胃腸の働きが低下し、吐き気を感じることがあります。プレゼン前や大事な試験の直前に、ムカムカしたり食欲がなくなるのも、その一例です。このようなストレスによる吐き気は、休息や気分転換などで改善することがありますが、症状が続く場合は早めに医療機関へ相談しましょう。
睡眠不足
睡眠不足が続くと、自律神経の乱れにより胃腸の働きが弱まり、吐き気を感じることがあります。特に、寝不足の朝にムカムカしたり食欲が出ない場合は、睡眠の影響が考えられます。また、慢性的な睡眠不足は体の回復力を下げ、ストレスにも敏感になり、体調不良の原因になることがあります。こうした不調を防ぐには、十分な睡眠と規則正しい生活を心がけることが大切です。
飲酒・喫煙
アルコールやたばこは胃腸に刺激を与え、吐き気の原因になることがあります。飲酒後にムカムカしたり、喫煙直後に気分が悪くなるのはその一例です。特に、空腹時の飲酒や過度のアルコール摂取は胃の粘膜を傷つけやすく、吐き気を引き起こしやすくなります。喫煙も胃酸の分泌を促し、症状を悪化させることがあります。こうした場合は、飲酒や喫煙の習慣を見直すことが体調の改善につながります。症状が続くときは、早めに医療機関に相談しましょう。
薬の副作用
薬の副作用で吐き気が現れることは珍しくありません。特に、新しく薬を飲み始めた後や、服用量が変わった時に吐き気を感じた場合は、薬の影響が考えられます。抗生物質や鎮痛薬、糖尿病薬、抗がん剤、精神科の薬などは、吐き気を起こしやすい薬の例です。症状が出たときは、自己判断で薬をやめずに医師に相談しましょう。受診の際は、お薬手帳や現在使用中の薬(処方薬・市販薬を含む)を持参し、服用を始めた時期や症状のタイミングを伝えることが重要です。
悪阻(つわり)
妊娠初期には、ホルモンの影響で「つわり(悪阻)」が起こり、吐き気や嘔吐を感じることがよくあります。とくに妊娠5〜12週頃に多くみられ、朝に強く出ることもあります。症状が重く、水分も摂れない場合は「妊娠悪阻」と診断され、点滴治療などが必要になることがあります。また、妊娠中はX線検査や一部の薬の使用が制限されるため、医療機関では女性を診察する際、妊娠の可能性を常に考慮しています。妊娠にまだ気づいていない方もいるため、慎重な対応が求められます。
吐き気を伴う疾患とは
機能性ディスペプシア
 血液検査や胃カメラ検査では異常が見られないのに、吐き気や胃痛、胃もたれが続いている状態です。機能性胃腸症とも呼ばれます。
血液検査や胃カメラ検査では異常が見られないのに、吐き気や胃痛、胃もたれが続いている状態です。機能性胃腸症とも呼ばれます。
感染性胃腸炎
ウイルスや細菌感染が主な原因です。具体的には、ノロウイルスやアデノウイルスなどに感染します。吐き気以外に腹痛や下痢などの症状を伴います。
逆流性食道炎
 胃酸が食道側に逆流し炎症が起こります。食道がんの原因ともなり、吐き気以外に、胸やけ、喉の違和感、ゲップなどの症状があるため、生活の質が低下します。
胃酸が食道側に逆流し炎症が起こります。食道がんの原因ともなり、吐き気以外に、胸やけ、喉の違和感、ゲップなどの症状があるため、生活の質が低下します。
急性胃炎
ウイルス感染、細菌感染、暴飲暴食、ストレスなどによって起こります。吐き気以外に胸やけ、腹痛、下痢などの症状を伴います。
腸閉塞(イレウス)
腸の動きが悪くなる、腸が狭くなって内容物が詰まってしまう状態です。場合によっては腸管が破裂し腹膜炎を起こしていることもあります。腸閉塞を起こすと、吐き気以外に、腹部の膨満感、排便や排ガスが無くなるといった症状も見られます。
便秘症
便秘によって腹部膨満感、下腹部痛などの症状が出現します。基本的に、消化管の蠕動運動(ぜんどううんどう)が低下していることが多いので、酷くなると吐き気を伴うこともあります。また、便秘には大腸がんが隠れている場合があるので、「ずっと便秘だから大丈夫」と油断せず、一度、消化器内科専門医を受診しましょう。
虫垂炎
大腸の一番奥にある虫垂に炎症が起きると、右下腹部に強い痛みが現れ、吐き気を伴う場合もあります。放置すると、腹膜炎を併発し、緊急手術が必要になることもあります。
消化器の病気以外で吐き気を伴うものは?
高血圧症
生活習慣病のなかでも、自覚症状が少ない疾患とされている高血圧は、程度が酷くなると吐き気や頭痛、意識障害、視覚障害などを伴います。
良性発作性頭位めまい症
めまいと共に、吐き気を伴うことがあります。症状が長期継続することで生活の質が下がってしまいます。
心筋梗塞
動脈硬化や血栓によって心臓に血液を送る冠動脈血流が著しく低下し、心臓細胞の一部が壊死している状態です。吐き気以外に、激しい胸の痛みや背中や肩の痛みなどを伴います。
くも膜下出血
発症すると、症状として吐き気を伴う突発的な激しい頭痛を起こします。突然死の原因にもなる病気なので、緊急対応出来る医療機関を受診して下さい。
髄膜炎
本来はウイルスや細菌が進入できない脳の中の髄膜に何らかの菌が感染し、それが原因で炎症が起こった状態です。発熱や意識障害以外に、吐き気を伴うことがあります。
吐き気に加えてこんな症状はありませんか?
以下の症状が併発していないかチェックしてみて下さい。
- 嘔吐
- 吐血
- 頻繁な吐き気
- 長時間や長期間の吐き気
- 胃の不快感
- 腹痛
- 下痢・下血
- 胸やけ
- 頻回のゲップ
- 便秘
- 頭痛
- めまい
- 発熱
悪寒を伴う吐き気
吐き気に加えて悪寒(寒気や体の震えを感じる症状)がある場合は、体内で感染や炎症が生じている可能性があります。たとえば、風邪やインフルエンザ、感染性胃腸炎などでは、ウイルスや細菌に対する免疫反応として、吐き気・悪寒・発熱・全身のだるさなどが同時にあらわれることがあります。さらに、腎盂腎炎、胆嚢炎、虫垂炎(いわゆる盲腸)など、内臓の炎症が原因となって悪寒と吐き気が引き起こされることもあります。これらの疾患は放置すると症状が悪化し、重篤な状態に進行することがあるため、早めの対処が重要です。このように、悪寒を伴う吐き気は単なる胃の不調とは異なり、全身の異常を知らせるサインであることがあります。発熱や腹痛、嘔吐、意識がぼんやりするなどの症状が一緒にみられる場合は、速やかに医療機関を受診してください。
吐き気の治療
機能性ディスペプシア
胃酸分泌を抑える薬、胃腸の働きを正常化する薬を用いた治療を行います。
感染性胃腸炎
積極的な水分摂取と安静が基本的対処法です。細菌感染の場合は、抗菌薬などを用いることもあります。
逆流性食道炎
胃酸分泌を抑える薬、吐き気を抑える薬、胃の働きを良くする薬で治療しながら、食生活などの生活習慣を改善していきます。
急性胃炎
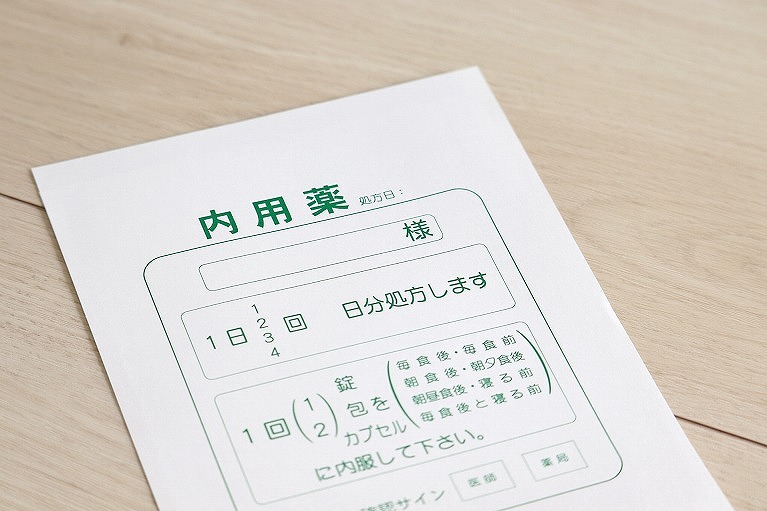 胃酸分泌や吐き気を抑える薬を用いて治療します。食事管理やアルコールの適量摂取、ストレスとの上手な付き合い方についてアドバイスを行います。
胃酸分泌や吐き気を抑える薬を用いて治療します。食事管理やアルコールの適量摂取、ストレスとの上手な付き合い方についてアドバイスを行います。
便秘症
腸の働きを正常化する薬、便の硬さを調整する薬を必要に応じて使用します。他疾患による便秘の場合は、その疾患の治療を行います。
虫垂炎
軽症の場合は、抗菌薬を用いた治療を行います。重症化して、腹膜炎を併発するような場合は、手術が必要ですので、専門の医療機関を紹介します。
高血圧症
血圧をコントロールする薬を用いて治療します。加えて生活習慣の改善を行います。
良性発作性頭位めまい症
 症状に応じて、抗めまい薬や抗不安薬などの使用が有効です。内服治療にて改善が乏しい場合は耳鼻科受診をおすすめします。
症状に応じて、抗めまい薬や抗不安薬などの使用が有効です。内服治療にて改善が乏しい場合は耳鼻科受診をおすすめします。
腸閉塞(イレウス)
イレウス管の挿入、絶食上での点滴管理、場合によっては手術が必要なこともあります。入院が必要なので専門の医療機関を紹介します。
心筋梗塞
バルーンやステントを用いた治療を行います。専門の医療機関を紹介します。
吐き気の漢方治療
吐き気に対する治療では、西洋薬に加えて漢方薬が使われることがあります。漢方薬は複数の生薬から成り、胃腸の調整やストレスに関連する症状の緩和に用いられます。代表的な処方には、食欲不振や胃の不快感に使われる六君子湯、喉のつかえ感や緊張による吐き気に使われる半夏厚朴湯、胃のムカつきや軟便を伴う場合の半夏瀉心湯などがあります。つわりや機能性ディスペプシア、ストレス性の吐き気などで西洋薬の効果が不十分な際に、補助的に用いられることがあります。保険適用の漢方薬も多く、副作用は比較的少ないとされますが、体質や症状によって合わないこともあるため、医師の判断に基づいて使用することが重要です。
胸やけ
暴飲暴食による一時的な胸やけは、特に心配する必要もありません。長時間にわたって胸やけの症状がある場合や、頻繁に胸やけが起こる場合には一度検査にお越しください。
疑われる病気は、逆流性食道炎、非びらん性胃食道逆流症、慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、食道がんなどです。
胸やけの疾患以外の原因
食生活
食生活が原因で胸やけが起こることがあります。特に、脂っこい料理や甘いもの、香辛料、炭酸飲料そしてカフェインを含む飲み物(コーヒー、紅茶、緑茶など)は、胃酸の分泌を促し、胃の働きを乱すことで症状を引き起こしやすくなります。また、早食いや過食、寝る直前の飲食も胃に負担をかけ、胃酸の逆流を招きやすくなります。食後すぐに横になることも注意が必要です。このように、食事の内容だけでなく、食べ方や時間帯も胸やけの要因になります。予防には、刺激の強い食品を控え、よく噛んでゆっくり食べること、食後しばらく横にならないことが効果的です。
精神的なストレス
精神的なストレスが引き金となって、胸やけの症状があらわれることがあります。強い緊張や不安が続くと、自律神経の働きが乱れ、胃酸の分泌が増えたり、胃の動きが鈍くなったりすることで、胸やけを感じやすくなります。このようなストレス性の胸やけは、休養やリラックスできる時間を確保することで改善することがあります。症状が長引く場合には、早めに医療機関を受診し、適切な評価を受けることが大切です。
睡眠不足
睡眠不足が続くと自律神経が乱れ、胃酸の分泌が増えたり、胃の動きが低下したりして、胸やけの原因になることがあります。さらに、睡眠不足はストレスの蓄積にもつながり、症状を悪化させることがあります。特に、夜更かしや夜間の間食が習慣になっていると、胃に負担がかかりやすく、胸やけが起こりやすくなります。予防には、十分な睡眠と規則正しい生活を心がけることが大切です。
飲酒・喫煙
アルコールやたばこは、明らかな疾患がなくても胸やけを引き起こすことがあります。飲酒は胃酸の分泌を増やし、胃の粘膜を刺激することで、胃酸の逆流を起こしやすくします。特に空腹時や過度の飲酒は注意が必要です。喫煙も、食道と胃の間の括約筋をゆるめ、逆流を促す要因になります。さらに、消化機能全体に悪影響を及ぼすことから、胸やけが続く場合は飲酒や喫煙の習慣を見直すことが大切です。
薬の副作用
一部の薬には、副作用として胸やけを引き起こすものがあります。カルシウム拮抗薬、気管支拡張薬、抗コリン薬、NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)などは、胃酸の逆流を防ぐ働きを弱めたり、胃粘膜を刺激することで症状を誘発しやすくなります。特に、空腹時の服用や長期使用は胸やけが起こりやすくなるため注意が必要です。薬が原因と思われる場合は、自己判断で中止せず、医師や薬剤師に相談しましょう。薬の変更や服用方法の調整で改善が期待できることもあります。
姿勢
胸やけは、体の姿勢によって悪化することがあります。とくに、前かがみの姿勢や、長時間座ったままで背中が丸まっている状態では、腹部が圧迫され、胃酸が食道へ逆流しやすくなります。さらに、ベルトの締めすぎや、ウエスト周りを強く圧迫する服装も、逆流を引き起こす要因となることがあります。このように、姿勢や衣類の圧迫が胸やけの原因になることがあるため、予防のためには背筋をまっすぐに保ち、腹部を締めつけない服装を選ぶことが大切です。
加齢
年齢を重ねると、胃と食道の間にある下部食道括約筋の機能が衰え、胃酸が食道へ逆流しやすくなることがあります。さらに、食道や胃の動き(蠕動運動)も弱くなり、逆流した胃酸が食道に長くとどまることで、胸やけが起こりやすくなります。また、加齢によって感覚が鈍くなると、胃酸の逆流があっても自覚しにくくなり、症状が慢性的に続いてしまうこともあります。このように、加齢は胸やけの発生や悪化に関係するため、姿勢の改善、ゆっくりよく噛んで食べること、寝るときの体の角度に配慮するなど、日常生活の中での対策が重要です。
胸やけに加えてこんな症状はありませんか?
げっぷ
食後に出るゲップは、食事中に空気を飲み込んでしまったために起こるものなので特に心配する必要はありません。げっぷが頻繁に起こるときは、胃の機能が低下している場合があります。
げっぷで疑われる病気は、慢性胃炎、機能性ディスペプシア、胃潰瘍、呑気症、胃がんなどです。
呑酸
呑酸は、げっぷとともに胃の内容物が口やのど元にせりあがってくるような症状です。逆流性食道炎や非びらん性胃食道逆流症、胃潰瘍、十二指腸潰瘍などの病気が考えられます。
のどがつかえる
医学的に「嚥下困難」と呼ばれます。ストレスや不安によって一時的にのどがつかえるような症状があらわれることがあります。また、加齢によって唾液量が減って飲み込みにくくなるような場合もありますが、それほど心配する必要はありません。
急にのどのつかえが酷くなったり、のどに変な突っかかりがある、痛みを伴うといった場合には、逆流性食道炎、非びらん性胃食道逆流症、食道裂肛ヘルニア、胃がん、食道がんなどの病気が疑われるので、検査にお越しください。
のどの違和感
のどの違和感の症状は、のど以外の耳や鼻、ストレスなど様々な原因で起こっていると考えられます。
のどの違和感が長く続いて、さらにのどや耳、鼻に特に異常が見つからない場合は、消化器の病気で症状がでている可能性があります。
のどの違和感で考えられる消化器の病気は、逆流性食道炎、非びらん性胃食道逆流症、食道がんなどです。
胸やけを伴う疾患とは
逆流性食道炎
逆流性食道炎は、胃酸や胃の内容物が食道に逆流することで起こる疾患です。胸やけや酸っぱいものが上がる感じ(呑酸)、のどの違和感、咳などの症状がみられます。とくに食後に症状が強まる傾向があります。
非びらん性胃食道逆流症
非びらん性胃食道逆流症は、内視鏡検査で粘膜に炎症などの異常が見られないにもかかわらず、胸やけや呑酸、胸やみぞおちの痛みといった逆流に関連する症状が現れる疾患です。主な原因として、食道がわずかな刺激に過敏に反応する「知覚過敏」や、食道の運動機能の低下が関係していると考えられています。
慢性胃炎
慢性胃炎では、胸やけやげっぷ、胃もたれ、胃の痛み、吐き気、お腹の張りなどの症状がみられます。原因の多くはピロリ菌感染によるもので、他にも過度な飲食やストレス、鎮痛薬の長期使用が関係します。炎症が長く続くと胃粘膜が萎縮し、進行すると胃がんのリスクが高くなるため注意が必要です。
食道アカラシア
食道アカラシアは、食道と胃のつなぎ目にある下部食道括約筋がうまく開かず、食べ物が胃に送られにくくなる疾患です。原因には食道の神経の異常が関与しており、主な症状には食べ物の飲み込みにくさ、胸やけ、胸のつかえ感、体重減少などがあります。胃カメラやバリウム検査で特徴的な所見が得られることもありますが、確定診断には「食道内圧検査(マノメトリー)」という特殊な検査が必要です。早期発見と適切な治療が重要です。
機能性ディスペプシア
機能性ディスペプシアは、内視鏡などの検査で異常が見つからないにもかかわらず、胃もたれや胸やけ、みぞおちの不快感などが続く疾患です。原因としては、ストレスや生活習慣の乱れ、胃の運動機能低下や知覚過敏などが関与していると考えられています。診断には他の疾患を除外する必要があり、治療には生活習慣の見直しや薬物療法が用いられます。
胃・十二指腸潰瘍
胃・十二指腸潰瘍は、胃酸の影響によって粘膜がただれたり欠損したりする疾患です。主な原因はピロリ菌感染で、他にも鎮痛薬の長期使用、飲酒・喫煙、ストレスなどが関係します。みぞおちの痛みや胸やけ、胃もたれ、膨満感、黒色便(タール便)などの症状が現れることがあります。適切な治療を行わないと再発や出血を起こすこともあるため、早めの受診が大切です。
食道がん
食道がんは、食道の粘膜に発生する悪性腫瘍で、進行すると周囲の臓器やリンパ節、肝臓・肺などへ転移しやすい特徴があります。初期には胸やけやのどの違和感、胸のつかえ感といった症状がみられることもあります。喫煙や多量の飲酒、熱い飲食物、逆流性食道炎、バレット食道、食道アカラシアなどが発症リスクを高める要因とされています。特に飲酒で顔が赤くなる方は、アルコール代謝で生じる発がん性物質アセトアルデヒドの分解が遅いため、体内に長く留まり、食道がんのリスクが高まると考えられています。
狭心症・心筋梗塞
狭心症や心筋梗塞などの心疾患でも、胸やけに似た症状が現れることがあります。胸の圧迫感や痛みに加え、左胸や肩の痛み、運動時の息苦しさなどが見られる場合は、消化器疾患だけでなく心臓の病気も疑う必要があります。とくに症状が運動後に強くなる場合は、早めの循環器受診が勧められます。
男性に多い胸やけ
胸やけは男女ともに起こり得る症状ですが、男性の方が発症しやすい傾向があるとされています。とくに働き盛りの男性では、偏った食生活やアルコールの過剰摂取、喫煙、精神的ストレスが重なりやすく、逆流性食道炎などの原因になることがあります。また、症状があっても受診を先延ばしにしやすいことから、気づいた時には慢性化しているケースも見られます。継続的な胸やけには、消化器の疾患に加えて狭心症などの循環器疾患が隠れている場合もあるため、症状が続くときは早めの受診が重要です。
女性に多い胸やけ
胸やけは女性にも多く見られる症状で、特に更年期の前後や中高年層の女性に発症しやすい傾向があります。これは、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌バランスが変化することで、胃腸の運動が不安定になりやすくなるため、胃酸の逆流や胃もたれを引き起こす原因となると考えられています。さらに、便秘や冷え、自律神経の乱れといった女性に多い身体的特徴が、胃腸の働きを弱め、胸やけを生じる一因になることもあります。加えて、無理なダイエットや過度な食事制限、心理的なストレスが消化機能を妨げ、逆流症状を悪化させることがあるため注意が必要です。症状が続く場合には、逆流性食道炎や機能性ディスペプシアなどの疾患が隠れている可能性もあるため、早めに医療機関を受診し、適切な評価を受けることが重要です。
胸やけの治療
胸やけの治療では、まずは日常生活の改善が基本方針となります。揚げ物など脂質の多い食事、アルコールやたばこの摂取、寝る直前の食事などは、胃酸の逆流を引き起こしやすく、胸やけの要因となるため注意が必要です。そのため、規則正しい食生活や適切な生活リズムを整えることが、改善の第一歩となります。こうした生活習慣の見直しに加え、必要に応じて胃酸分泌を抑える薬(PPIやH2ブロッカーなど)や、胃の運動をサポートする薬剤を使用することがあります。当院では、薬物療法に頼りきるのではなく、根本的な原因への対処を重視する方針をとっています。なお、症状が長引く場合や、胸やけ以外の症状(胸の痛み、食欲低下、体重減少など)が伴うときには、胃内視鏡(胃カメラ)による精密検査が必要になる場合もあります。当クリニックでは内視鏡検査は実施しておりませんが、内視鏡検査が必要と考えられる際には、提携している専門医療機関をご紹介していますので、どうぞ安心してご相談ください。
胃もたれ・膨満感
胃の機能が何かしらの理由で低下すると、十二指腸に胃の内容物を送り出す働きが弱くなり、食後に胃がもたれたり膨満感が起こります。
胃もたれ・膨満感で疑われる病気は、慢性胃炎、機能性ディスペプシア、胃潰瘍、胃がんなどです。
胃もたれに伴う症状
食欲不振
食欲不振はストレスのほか、慢性胃炎や急性胃炎、機能性ディスペプシアなどが原因で起こります。1週間以上、食欲不振や体重が急に減ったなどの症状があらわれた場合は、胃がんやすい臓がんなどの重篤な病気も考えられます。
嘔吐
嘔吐の症状がおこる消化器疾患は、急性胃炎、慢性胃炎、急性腸炎、胃潰瘍、逆流性食道炎、非びらん性胃食道逆流症、腹膜炎、腸閉塞、虫垂炎など様々です。
検査で原因を調べて適切な治療を行うことが重要です。
吐血
吐血は、見た目から出血箇所をある程度特定することができます。胃、十二指腸から出血が起こると、黒くなった血を吐きます。食道からの出血は、鮮血(真っ赤な血)を吐きます。
吐血すると、血圧低下、頻脈、立ちくらみなどを伴うことがあります。
急性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がん、食道がん、マロリー・ワイス症候群などの病気が疑われます。
下血(血便)
食道、胃、十二指腸から出血が起こると、黒っぽい便(タール便)が出ることがあります。胃や十二指腸に穴があいている場合もあるので、黒っぽい便が出たときにはなるべく早めに胃カメラ検査を受けることをお勧めします。
黒っぽい血便が出たときは、急性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がんなどの病気が疑われます。
よくある質問
吐き気はストレスが限界に近いときに現れるものですか?
はい、強いストレスや緊張状態が続くと、身体にさまざまな不調が出ることがあり、その一つとして吐き気を感じることがあります。ストレスにより自律神経のバランスが乱れると、胃腸の動きが悪くなり、ムカムカしたり食欲が落ちたりすることがあります。たとえば、大切な予定の前に気分が悪くなるのもその一例です。こうした症状が何度も起こる場合には、心身の負担が大きくなっている可能性があるため、休息をとったり、必要に応じて医療機関へ相談することが大切です。
食後しばらくしてから気持ち悪くなるのはなぜですか?
食後2〜3時間ほど経ってからムカムカする場合、胃の動きが鈍く、消化がスムーズに進んでいない可能性があります。脂質の多い食事や早食いなどが原因で、胃に食べ物が長く留まり、胃もたれや吐き気につながることがあります。また、逆流性食道炎や機能性ディスペプシアなどの消化器疾患が関与している場合もあります。症状が繰り返されるようであれば、消化器内科での診察を検討しましょう。
吐き気を和らげるにはどうすればいいですか?
吐き気があるときには、以下のような方法で症状が軽くなることがあります。
- 静かな場所でリラックスして深呼吸をする
- 背中を伸ばして座るか、上半身を少し起こした状態で横になる
- においや刺激の強い食べ物・飲み物(カフェイン、香辛料など)を避ける
- 冷たい水を少しずつ飲む
なお、吐き気が何日も続いたり、発熱・腹痛・頭痛などの症状が併発する場合は、早めの受診が必要です。
えずきを抑える方法には何がありますか?
えずき(吐き気が強まって喉が締めつけられるような感覚)は、胃の不快感や緊張、喉の違和感などから起こることがあります。以下のような方法で落ち着くことがあります。
- 鼻から吸って口からゆっくり吐く深呼吸を数回行う
- 首元を温めてリラックスさせる
- 姿勢を正して腹部を圧迫しないようにする
えずきが頻繁に起きる場合は、逆流性食道炎やストレス性胃腸障害、咽頭の緊張が関係している可能性もあるため、消化器科や内科での相談が勧められます。
吐き気が強いとき、どんな姿勢をとると楽になりますか?
吐き気が強いときには、以下のような姿勢をとると症状が軽くなることがあります。
- 背中にクッションなどを当てて、上半身を30〜45度起こして横になる
- 横向きになって、少し前屈みの姿勢を保つ(嘔吐時の誤嚥を防ぐため)
- 椅子に座って背筋をまっすぐ伸ばす
また、食後すぐに横になると胃酸が逆流しやすくなるため、しばらくは体を起こして過ごすのが望ましいです。
嘔吐の後に飲むのに適した飲み物はありますか?
嘔吐後は体が脱水気味になっていることが多いため、水分補給が重要です。ただし、一度にたくさん飲むのではなく、少しずつゆっくり飲むようにしましょう。以下の飲み物がおすすめです。
- 常温の水
- 経口補水液(OS-1など)
- 薄めたスポーツドリンク
- カフェインを含まない麦茶やほうじ茶
逆に、炭酸飲料、コーヒー、アルコールなど刺激の強い飲み物は避けたほうが安心です。
吐き気があるとき、吐いた方がよいのでしょうか?
吐き気が強く、自然に吐きそうなときには無理に我慢せず、吐いてしまった方が楽になることもあります。ただし、頻繁に吐く、血が混じる、脱水の兆候(ふらつき・口の渇きなど)があるときは、すぐに医療機関を受診してください。吐いた後は水分をこまめに補給し、安静に過ごすことが大切です。原因がわからないまま吐き気が続く場合には、専門的な検査が必要です。