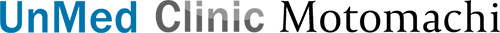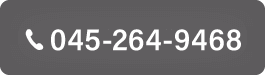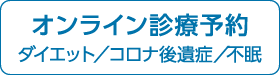逆流性食道炎とは
 胃から何らかの原因で胃酸が食道に逆流することで、食道に炎症が生じる疾患を逆流性食道炎と言います。特に、しつこい胸やけが特徴で、そのほか呑酸(どんさん:苦味や酸味を感じる)、ゲップ、胸部の痛み、咳など、酷くなると日常生活に支障が出る程の辛い症状です。
胃から何らかの原因で胃酸が食道に逆流することで、食道に炎症が生じる疾患を逆流性食道炎と言います。特に、しつこい胸やけが特徴で、そのほか呑酸(どんさん:苦味や酸味を感じる)、ゲップ、胸部の痛み、咳など、酷くなると日常生活に支障が出る程の辛い症状です。
胃の粘膜は強くて厚い構造ですが、食道の粘膜は薄く胃酸に弱い構造をしています。そのため、胃酸が食道に逆流すると容易に炎症を起こします。さらに、逆流性食道炎が長期化すると、いずれバレット食道癌に発展するリスクがあります。再発しやすいことも特徴なので、食道癌リスクを回避するためにも定期的な検査と適切な治療が大切です。
診断
逆流性食道炎は症状をお聞きし、問診を重点的に行います。
問診から、必要に応じて検査を実施します。
※胃カメラ(胃内視鏡検査)が必要となった場合は近隣の連携医療機関で検査を受けて頂けます。
セルフチェック・Fスケール
逆流性食道炎は「Fスケール」というセルフチェック項目があります。合計8点以上の方は、逆流性食道炎の可能性があるのでチェックしてみて下さい。
| 質問 | ない | 稀に | 時々 | しばしば | いつも |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.胸焼けがしますか? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.お腹が張ることがありますか? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.食事をした後に胃がもたれる(重苦しい)ことはありますか? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.思わず手のひらで胸をこすってしまうことがありますか? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.食べた後、気持ち悪くなることがありますか? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.食後に胸やけが起こりますか? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.喉の違和感がありますか? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8.食事の途中で満腹になってしまいますか? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9.ものを飲み込むと、つかえることがありますか? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10.苦い水(胃酸)が上がってくることがありますか? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11.ゲップがよく出ますか? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12.前かがみをすると胸やけがしますか? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
※横スクロールで全体を表示
逆流性食道炎の症状
- 胸やけ
- 口に胃酸(すっぱい苦い液体)がこみ上げてくる
- 胸の締め付けられるような痛み
- ゲップが多い
- お腹の張り
- 胃もたれ
- 喉の違和感
- 咳が出る
- 声がかすれる
逆流性食道炎の原因
逆流性食道炎の主な原因として、年齢変化によるもの、生活習慣などの行動によるもの、そのときの体質によって胃酸が逆流しやすくなると考えられています。
年齢変化によるもの
年齢を重ねることによって、食道括約筋が緩み、食道と胃のつなぎ目がしっかり閉まっているはずが弱くなり胃酸が逆流します。
生活習慣によるもの
私たちの生活習慣によって、胃の内圧が上がったり、胃酸の分泌量が増えたり、胃の動きが悪くなり食べ物が胃内に停滞してしまうと症状が現れます。
- 脂肪の多い食事、餅など消化が悪い食事
- 甘い食べ物や辛い食べ物の過度な摂取
- 酸っぱい食べ物の過度な摂取
- コーヒーや紅茶などの過度な摂取
- 飲酒喫煙、嗜好品(しこうひん)の摂取
- 肥満や妊娠、便秘などの体質によるもの

以上のような生活習慣により腹圧が高まり、胃酸が逆流しやすくなります。
薬剤によるもの
逆流性食道炎は、使用している薬の影響で起こることもあります。たとえば、胃腸の運動を抑える目的で使用される抗コリン薬や、頻尿の治療薬として処方されることがある薬剤は、食道下部の括約筋の働きを弱めることがあり、胃酸の逆流を引き起こしやすくなります。
また、高血圧の治療に用いられるカルシウム拮抗薬や、狭心症などの治療に使われる硝酸薬(亜硝酸薬)も、同様に括約筋の緩みを誘発する可能性があります。さらに、経口避妊薬(低用量ピルなど)も、ホルモンバランスの変化により逆流症状を悪化させる場合があります。
他の疾患によるもの
食道裂孔ヘルニア
食道裂孔ヘルニアは、通常お腹の中にある胃の一部が、横隔膜(お腹と胸を仕切る筋肉)のすき間から胸の方へ移動してしまう状態を指します。このような状態になると、胃と食道の境目がゆるくなりやすくなり、胃の中の酸が食道に逆流しやすくなります。このタイプの構造的な異常は、逆流性食道炎の原因としてよく見られるものの一つです。
糖尿病
糖尿病が長期間続くと、自律神経(体のさまざまな機能を無意識に調整する神経)がうまく働かなくなることがあります。その結果として、胃や食道の動きが鈍くなり、食べたものが胃の中に長くとどまりやすくなります。このような状態では、胃の中の圧力が上がってしまい、胃酸が逆流しやすくなります。このため、糖尿病は逆流性食道炎の原因の一つとして知られています。
パーキンソン病・多系統萎縮症(MSA)
パーキンソン病や多系統萎縮症は、神経の働きが徐々に弱くなっていく進行性の病気です。これらの疾患では、手足の動きが悪くなるだけでなく、飲み込む力や胃腸の動きも低下してしまいます。そのため、胃酸が食道に逆流した際にうまく排出できず、食道にとどまりやすくなります。結果として、逆流性食道炎が起こりやすくなることがあります。特に高齢の方では見逃されがちな要因の一つです。
全身性強皮症
全身性強皮症は、皮膚や内臓が硬くなる自己免疫疾患で、免疫の異常な働きが関係しています。この疾患では、食道の筋肉が硬くなって動きが悪くなったり、胃と食道の境目がゆるんだりすることがあります。その結果、胃酸が逆流しやすくなり、逆流性食道炎を引き起こしやすくなります。
食道アカラシア
食道アカラシアは、食道の下の方にある筋肉(下部食道括約筋)がうまく開かず、食べ物が胃に送られにくくなる病気です。この状態では、食べ物や胃酸が食道にたまりやすくなり、食道の粘膜を刺激して炎症が起きやすくなります。そのため、食道アカラシアがあると逆流性食道炎の症状が強く出ることがあります。
混合性結合組織病(MCTD)
混合性結合組織病(MCTD)は、強皮症や全身性エリテマトーデス、多発性筋炎など、いくつかの自己免疫疾患の特徴が組み合わさって現れる病気です。この病気では、食道の動きが悪くなることがあり、それによって胃酸が逆流しやすくなります。その結果、逆流性食道炎の発症や悪化につながることがあります。
若い人に多い逆流性食道炎の原因
逆流性食道炎は高齢者に多い疾患というイメージがありますが、近年では20代から40代の若年層にも発症が増加しています。その背景には、乱れた生活リズムや食習慣、精神的ストレス、アルコールやカフェインの過剰摂取、そして腹圧の上昇といった日常的な要因があります。これらの要素は単独でも逆流の引き金になりますが、複数が重なるとより強く症状を引き起こす傾向があるため、注意が必要です。
食生活の乱れ(早食い・脂質の多い食事・夜食など)
若い世代では、忙しい毎日の中で食事の時間が不規則になったり、手軽な外食やコンビニ食に頼る機会が多くなりがちです。これにより、脂質の多い揚げ物やカロリーの高い加工食品に偏った食生活になり、胃腸に大きな負担をかけることになります。特に「早食い」は、よく噛まずに食べることで消化に時間がかかり、胃酸の分泌量も多くなりがちです。また、夜遅い時間に食事をとると、胃が働いている最中にすぐ横になることになり、重力による逆流防止効果が得られず、胃酸が上がりやすくなります。これは、夕食後2〜3時間空けずに就寝する人に特に多く見られます。逆流性食道炎を防ぐためには、食事の時間・内容・食べ方すべてを見直すことが重要です。
自律神経の乱れ(精神的なストレス・睡眠不足)
若年層は、人間関係での悩みや進学・就職に対する不安、仕事上のストレスなど、精神的な負担を受けやすい状況にあることが少なくありません。こうした心理的ストレスが継続すると、自律神経の働きが乱れ、胃や食道の動きが鈍くなります。その結果、胃の中に胃酸がとどまりやすくなり、逆流が起こりやすくなります。さらに、近年ではスマートフォンやパソコンの長時間使用により、就寝時間が遅くなる傾向があり、慢性的な睡眠不足に陥るケースも多く見られます。睡眠の質や時間が不足すると、自律神経のバランスがさらに崩れ、消化機能の低下を招くため、逆流性食道炎のリスクが一層高まります。
過剰な飲酒
若い世代では、飲み会やお酒の付き合いが多くなる時期でもあります。アルコールには、胃と食道の境目にある下部食道括約筋(LES)の働きをゆるめる作用があり、その結果、胃酸が食道に逆流しやすくなります。また、アルコールは胃粘膜を直接刺激して炎症を起こしやすくするため、胸やけや胃もたれの症状を引き起こすリスクもあります。特に、空腹時や深酒は注意が必要です。
カフェインや炭酸飲料の過剰摂取
エナジードリンクやコーヒー、炭酸飲料を日常的に摂取する若年層は多く見られます。カフェインは胃酸の分泌を促進し、下部食道括約筋の働きを弱めるため、胃酸が逆流しやすくなります。また、炭酸飲料に含まれるガスによって胃が膨らむと、腹圧が高まり逆流のリスクが増します。過剰摂取を続けると、知らないうちに逆流性食道炎の症状を引き起こす可能性があります。
腹圧の上昇(前かがみ姿勢・筋トレ・便秘など)
若い人でも、長時間のパソコン作業やスマートフォン使用によって猫背や前かがみの姿勢が続くことが多くあります。このような姿勢では、お腹が圧迫され、腹腔内圧(腹圧)が上昇しやすくなります。さらに、腹筋を中心とした筋トレや重い荷物の持ち上げ、便秘による強いいきみなども、同様に腹圧を高めます。腹圧が過剰にかかると、胃の内容物が押し上げられる形で食道へ逆流しやすくなります。特に便秘が慢性化している場合は、消化管の運動リズムが乱れて胃の排出にも影響が出やすく、逆流性食道炎の一因となることがあります。日常の姿勢改善や適度な運動、食物繊維の摂取など、腹圧をコントロールする生活習慣の見直しが予防につながります。
高齢者に多い逆流性食道炎の原因
高齢の方では、年齢を重ねることによって胃や食道の働きが弱まりやすくなります。さらに、慢性的な疾患の存在や加齢に伴う姿勢の変化、加えて服用している薬剤の影響など、さまざまな要因が複雑に関係することで、胃酸が逆流しやすい状態になり、逆流性食道炎を起こす可能性が高くなります。
加齢による消化機能の低下
高齢になると、食道や胃の筋肉が徐々に衰えていきます。その結果、飲食物や胃酸を食道から胃へ、さらに胃から小腸へと円滑に送り出す能力が低下しやすくなります。特に、胃と食道の接続部にある「下部食道括約筋(LES)」は、本来、胃酸が逆流しないように防ぐ弁の役割を果たしていますが、年齢とともにこの筋肉の収縮力が弱まり、胃酸や食物が食道内へ逆流しやすくなるのです。また、胃の内容物を排出する働き自体も加齢で低下しやすく、胃の中にとどまる時間が長くなることで胃内の圧力が上昇し、逆流を誘発します。加えて、唾液の分泌量も減少する傾向があり、唾液が持つ胃酸を中和・除去する機能が弱まるため、逆流した胃酸が食道粘膜を刺激しやすくなります。こうした一連の加齢による変化が、逆流性食道炎の発症や悪化に深く関係しています。
体の構造変化と姿勢による影響(食道裂孔ヘルニア・円背など)
加齢によって生じる体の構造的な変化も、逆流性食道炎のリスクを高める要因となります。代表的なものが「食道裂孔ヘルニア」で、これは横隔膜の筋肉や支持組織が緩むことで、胃の一部が胸側へはみ出してしまう状態です。この変化により、本来の逆流防止構造が崩れてしまい、胃酸や食物が食道に戻りやすくなります。とくに高齢者では、このような異常が無症状のまま進行することも多く、気づかないうちに食道の炎症が悪化していることもあります。さらに、加齢にともなう骨密度の低下(骨粗しょう症)や筋力低下、脊椎の変形などにより、自然と背中が丸まる「円背(猫背)」になりやすくなります。この姿勢は腹部に持続的な圧力をかけ、胃が上方向に押し上げられやすくなり、その結果、胃酸が食道に逆流しやすい状態になります。このように、加齢に伴う姿勢や構造の変化は、逆流性食道炎の一因となるため注意が必要です。
慢性疾患および服薬による影響(パーキンソン病・糖尿病など)
高齢者に多く見られる慢性疾患の中には、消化機能に影響を与えるものがあり、逆流性食道炎の原因となることがあります。たとえば、パーキンソン病を抱える方では、食道や胃の蠕動運動が低下し、食べたものが胃内にとどまる時間が長くなる傾向があります。その結果、胃内圧が高まり、逆流が起こりやすくなります。一方、糖尿病の患者では、自律神経障害により胃の排出が遅れる「胃排出遅延(ガストロパレシス)」を生じることがあり、これも逆流のリスク要因となります。さらに、これらの疾患に対して処方される薬剤には、下部食道括約筋の機能を低下させる副作用を持つものが含まれています。具体的には、抗コリン薬、カルシウム拮抗薬、硝酸薬などが該当し、いずれも胃酸の逆流を助長するおそれがあります。このため、高齢者の逆流性食道炎を考える際には、基礎疾患の影響だけでなく、服用中の薬剤についても慎重な確認が求められます。
逆流性食道炎の治療
逆流性食道炎は、生活習慣を改善しながら経過を見ていきますが、それでも症状が改善しない場合には薬物治療を導入致します。
生活習慣の改善
生活習慣の改善とは、胃酸が逆流しないように、些細なことに気を配ることが大切です。例えば、食後にすぐ横にならない、腹圧が上がりやすい動作に注意すること(前かがみの姿勢・草むしり・ベルトの締め過ぎなど)などを生活の中で避けるようにしましょう。これらに注意するだけでも、胃酸の逆流防止に繋がります。また、胃酸の逆流を引き起こしやすい食べ物などを以下に挙げてみます。
- チョコレート
- ケーキ
- アイスクリーム
- 餡子菓子
- コーヒー(カフェイン)
- ココア
- 酸っぱい食べ物(梅干しや柑橘類)
- アルコール
- 炭酸類
- たばこ など。
以上のように、高脂肪食品や消化の悪い食事、刺激の強い食品、お酒、たばこなどを控え、コーヒーや紅茶などを飲む回数を減らしたりして食生活の改善を図りましょう。
薬物療法
食生活などの生活習慣の改善を図ってもあまり症状が治まらない場合は、薬物療法で症状の緩和を促します。患者さんの症状や原因に応じて、適切な内服薬を処方します。
- 胃酸分泌抑制薬:胃酸を少なくして食道の炎症を抑えます。
- 消化管運動機能促進薬:胃や食道に停滞している食べ物を十二指腸以下に送り出す蠕動運動(ぜんどううんどう)を促進させます。
基本的に、1つの薬剤で治療を始めますが、症状が改善しないときは効果の違う薬を併用していきます。治療効果がより高まるよう、患者さんの症状に合わせて治療薬を選択していきます。
漢方
逆流性食道炎の治療では、一般的に胃酸の分泌を抑える薬(プロトンポンプ阻害薬など)による治療が行われますが、漢方薬を用いることも一つの選択肢です。漢方では、胃腸の機能低下やストレス、冷えといった体質的な要因を考慮し、症状の背景に応じて処方が行われます。漢方薬は、同じような症状でも体質や全身状態によって適したものが異なるため、服用を検討する際は医師や薬剤師に相談し、自分に合った処方を受けることが大切です。また、漢方薬にも副作用や他の薬との相互作用のリスクがあるため、自己判断での使用は避け、専門的な指導のもとで安全に使用するようにしましょう。
半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)
半夏厚朴湯とは、精神的な緊張や不安を感じやすく、喉のつかえ感や冷え性がみられる方に適した漢方薬です。自律神経の乱れからくる気分の落ち込みや吐き気、咳などの症状をやわらげる働きがあり、体内の「気」の流れを整えることで心身のバランスを改善します。また、水分の代謝を促進することで、胃腸の働きを助ける効果も期待されます。
六君子湯(りっくんしとう)
六君子湯とは、胃がもたれやすく、食欲不振や倦怠感が続く方、体力が乏しくやせ型の体質の方によく用いられる漢方薬です。消化吸収機能を高めて、胃腸の動きを活発にしながら、体内に余分な水分が停滞するのを防ぐ作用があります。とくに胃腸虚弱が原因で起こる不調の改善に用いられる、代表的な補剤です。
半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)
半夏瀉心湯とは、みぞおちの不快感やお腹の張り、軟便・下痢・腹部のゴロゴロ音といった症状がある方に適した漢方薬です。胃腸の機能を整えると同時に、炎症を抑える作用があり、吐き気や胃のつかえ感、食道の違和感なども軽減することが期待されます。比較的体力のある方に処方されることが多く、胃腸と神経の両面に働きかけるバランスの取れた処方です。
非びらん性胃食道逆流症(NERD)について
一般的な逆流性食道炎では、内視鏡で食道にびらんや炎症が確認されますが、症状があるのに内視鏡で異常が見られない場合があります。このようなケースは「非びらん性胃食道逆流症(NERD)」と呼ばれ、食道がわずかな刺激にも敏感に反応する「知覚過敏」が関係していると考えられています。NERDでは、胃酸の逆流量が少なくても症状が強く出ることがあり、胃酸を抑える薬(PPI)が効きにくい傾向があります。また、胃酸ではなく、アルカリ性の胆汁や膵液の逆流が原因となることもあります。逆流が続くと「バレット食道」に進行することがあり、この状態は将来的に食道がんのリスクを高めることがあるため、定期的な内視鏡検査が大切です。
よくある質問
逆流性食道炎の症状がある場合、何科を受診すればよいですか?
逆流性食道炎が疑われる場合は、「内科」または「消化器内科」を受診してください。継続的な胸やけや胃もたれ、喉の不快感などがある場合は、まず内科で相談し、必要に応じて詳しい検査(胃内視鏡など)を行うのが望ましいとされています。
胃カメラを受けたくない場合でも、逆流性食道炎の診断は可能ですか?
胃カメラを行わなくても、問診や症状に基づいたチェックリスト(例:Fスケール)を用いて診断がつくことはあります。ただし、症状が長引いている場合や治療効果が乏しい場合は、食道の状態を正確に把握するためにも内視鏡検査が推奨されます。当院では、胃カメラが必要と判断された場合には、提携する医療機関をご紹介し、検査がスムーズに受けられるよう体制を整えております。
逆流性食道炎のときに避けるべき行動はありますか?
次のような行動は、胃酸の逆流を促進する可能性があるため避けましょう。
- 食後すぐに横になる
- 長時間の前かがみの姿勢
- 過度な飲酒や喫煙
- 就寝直前の飲食や暴飲暴食
- ベルトを強く締めるなど、お腹を圧迫する行為
水を飲むことで逆流性食道炎の症状は治まりますか?
水を飲むことで一時的に症状が和らぐことはありますが、水だけで逆流性食道炎が根本的に治るわけではありません。継続的な症状がある場合は、生活習慣の見直しや医師の判断による治療が必要です。
胸やけなどの症状がある場合、病院へ行くべきでしょうか?
はい。症状が軽度でも繰り返すようであれば、自己判断せず医療機関を受診しましょう。特に、胸の痛み、喉の違和感、咳などが続く場合は、バレット食道などの病気が隠れていることもあるため、医師による評価が重要です。
逆流性食道炎を早く改善するにはどうすればよいですか?
就寝前の食事を控え、食後はしばらく座った姿勢で過ごすこと、ストレスをため込まないこと、正しい姿勢を意識することが有効です。薬による治療を並行して行うことで、症状の早期改善が期待できます。早めの医療機関への相談が大切です。
逆流性食道炎を放置しても問題ありませんか?
いいえ。放置することで、食道の炎症が慢性化し、バレット食道や食道がんといった重篤な疾患につながるおそれがあります。軽症でも継続的な症状がある場合は、早めに医師へ相談してください。
市販薬で逆流性食道炎は改善できますか?
一時的には、H2ブロッカーや制酸薬といった市販薬で症状が和らぐことはあります。ただし、症状が継続・悪化する場合は、市販薬に頼るのではなく、医師の診察と適切な治療を受けることをおすすめします。