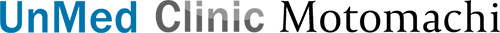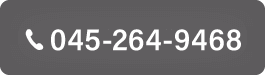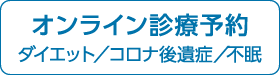胃痛・胃もたれはなぜ起こるのか
私たちの胃は、食べ物を一旦蓄えて、消化吸収の準備を行う臓器です。胃には胃液分泌と蠕動運動(ぜんどううんどう)によって食べ物を消化する働きがあります。3層の厚い筋肉でできた胃壁で覆われ、胃の内側は柔らかい粘膜に覆われています。
胃液は胃の粘膜から分泌され、胃酸・ペプシノーゲン・胃粘液の3つの成分で構成されています。
- 胃酸:消化酵素の活性化
- ペプシノーゲン:たんぱく質を分解する酵素
- 胃粘液:胃酸などから胃壁を守る
胃の働きはこれら胃液の仕組みがもたらす絶妙なバランスで保たれています。そのバランスが崩れると、胃痛や胃もたれ、胃炎や胃潰瘍などさまざまなトラブルが引き起こります。
胃痛は、みぞおち付近に現れる痛みを指しますが、胃痛の表現は人によって様々です。例えば、以下のように表現されることがあります。
- 鈍い痛みが継続して起こる→チクチク痛む
- 鋭い痛みが走る→キリキリ痛む
- 脈を打つように痛みが続く→胃がズキズキする
- 締め付けられるような痛み→胃がキューとなる
胃痛の原因は様々ですが、胃酸が過剰になることで胃粘膜が荒れて、ダメージを与えてしまうことが主な原因とされています。また、胃痛があっても胃の中は綺麗で、検査に異常が無いという方が割といらっしゃるのも特徴です。
一方、胃もたれは、食後によく胃が重い、ムカムカする、お腹が張るといった表現をされることが多いです。食べ物が胃に入り、消化をする際、何らかの原因によって胃の蠕動運動が妨げられ、幽門(ゆうもん:胃の出口付近)の動きが悪くなると胃の中に食べ物が貯留する時間が長くなるのが胃もたれの原因とされています。
すぐに病院に行くべき胃痛症状
- 吐血、下血、黒色便を伴う胃痛は、胃を含む上部消化管内で出血している可能性があります。
- 発熱を伴う胃痛は、胆のう炎、膵炎、虫垂炎、腹膜炎などの可能性があります。
- 突然激しい胃痛に襲われる場合は、アニサキスによる食中毒、胆のう結石や血栓症などの可能性があります。また、頻度は低いですが、急性虫垂炎で胃痛症状が出ることもあります。
- 排ガスや排便が止まっている中で胃痛、嘔吐を繰り返す場合は腸が詰まっている(腸閉塞の)可能性があります。
以上の症状は、緊急を要する疾患の可能性があるので、すぐに病院を受診して下さい。
胃痛・胃もたれ症状で多い病気とは?
1.急性胃腸炎
暴飲暴食、脂っこい物や香辛料などの刺激物の過剰摂取、アルコール多飲の他、細菌やウイルス感染などが要因で発症します。胃酸分泌が過剰になったり、病原体によって胃粘膜が傷つくことで起こります。
2.慢性胃炎
急性胃炎を繰り返すことやピロリ菌感染によって胃粘膜障害が慢性化することが原因です。長期的なストレスも要因となり発症します。
3.胃・十二指腸潰瘍
慢性的なストレス、ピロリ菌感染、解熱鎮痛剤の過量服用などによって起こります。過剰な胃酸や薬の刺激が胃粘膜を傷つけ、それが長く続くと潰瘍ができます。
4.胃がん
胃がんとは、胃の内側の粘膜に発生する悪性腫瘍で、多くはヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)の感染および喫煙が関係しています。ピロリ菌に感染していない方や非喫煙者の発症リスクは低く、日本では肺がん・大腸がんに次いで死亡数が多いがんですが、ピロリ菌の除菌治療の普及などにより発症数は減少傾向にあります。早期の胃がんは自覚症状が乏しい一方、進行すると胃痛や胃もたれ、食欲不振などの症状が出ることがあり、これらは胃がんが原因となる場合もあります。ただし、症状だけで診断するのは難しく、多くは内視鏡検査(胃カメラ)で発見されます。
5.機能性ディスペプシア
機能性ディスペプシアとは、内視鏡などの検査では異常が見つからないにもかかわらず、胃痛や胃もたれなどの症状が続く状態を指します。胃の動きが鈍くなったり、胃酸に対して過敏に反応したりすることで、食後のもたれ感やみぞおちの痛み、早期の満腹感などが現れます。このような症状の改善には、胃の働きを整える薬や胃酸の分泌を抑える薬が使われます。必要に応じて、六君子湯などの漢方薬や、ストレスの影響が大きい場合は抗不安薬などが用いられることもあります。再発を繰り返す傾向があるため、治療には薬だけでなく、食生活の見直しや生活リズムの改善、ストレス対策などもあわせて行うことが大切です。
6.逆流性食道炎(GERD)
逆流性食道炎とは、胃酸や胃の内容物が食道へ逆流し、食道の粘膜に炎症を起こす疾患です。
通常、食道と胃の間には「下部食道括約筋」があり、胃の内容物が逆流しないように働いています。しかし、この筋肉の機能が低下すると、胃酸が食道に逆流しやすくなり、胸やけや呑酸などの症状が生じます。逆流性食道炎は、こうした典型的な症状に加え、胃痛や胃もたれの原因となることもあります。特に食後や横になったときに症状が出やすく、慢性的な胃の不快感が続く場合は、逆流性食道炎の可能性を考えて医療機関での診察が必要です。
7.膵炎
膵炎とは、膵臓に炎症が起こる疾患で、胃痛や胃もたれの原因となることがあります。
膵臓は胃の裏側にある臓器で、消化酵素や血糖を調整するホルモンを分泌しています。膵炎には、急に激しい痛みが出る急性膵炎と、軽い腹痛や膨満感が繰り返される慢性膵炎があります。主な原因には、多量の飲酒や胆石、高脂血症などがあり、重症化すると命に関わることもあるため注意が必要です。胃の不調が続く場合は、膵臓の病気も考慮して医療機関を受診しましょう。
8.胆のう炎・胆石症
胆のう炎・胆石症とは、胆のうや胆管に異常が起こる疾患で、胃痛や胃もたれの原因になることがあります。胆のうは肝臓の下にある袋状の臓器で、胆汁を蓄え、消化を助ける役割があります。胆石症は胆のうや胆管に石(胆石)ができる状態で、胆のう炎はその石などによって炎症が起こるものです。これらの疾患では、特に脂っこい食事の後に、みぞおちや右上腹部に痛みや重苦しさが現れ、胃痛や胃もたれとして感じられることがあります。症状が繰り返される場合は、胆のうや胆管の異常が関係している可能性があるため、医療機関での検査をおすすめします。
9.食中毒
とくに胃痛を引き起こす食中毒は、アニサキスやカンピロバクターです。
この他、逆流性食道炎も胃痛の原因になります。
胃痛・胃もたれを起こす病気以外の原因とは?
1.暴飲暴食・脂っこい物の過剰摂取
摂取した脂肪分の多くは胃で分解されずそのまま十二指腸へ送られます。十二指腸で脂肪分解のための消化酵素が分泌されます。この消化酵素には胃の蠕動運動を抑制する働きがあるため、脂肪分を多く摂取すると、この消化酵素が過剰に分泌され、その結果、胃の動きが悪くなり、胃内に食べ物が長時間残ってしまうため、胃もたれの症状が出ます。
2.アルコール多量摂取
アルコール摂取が多量かつ高濃度の場合、直接的に胃粘膜障害を起こします。これが胃もたれの原因になります。
3.加齢
加齢に伴って、消化管機能が低下します。胃の弾力性も低下し、以前と同じ量の食べ物を消化することが出来ず、小腸に送り出す速度も低下し胃の中に食べ物が長時間滞在するので胃もたれを起こします。
4.その他
胃の運動機能異常、内臓の知覚過敏、過度なストレスなど様々な因子が関連しています。また、女性では月経前のホルモンバランスの変化(PMS:月経前症候群)により、胃の不快感や消化器症状が出やすくなることもあります。
PMSと胃痛・胃もたれ
PMS(月経前症候群)とは、生理の数日前からあらわれる身体的および精神的な不調のことを指します。これは女性ホルモンの変動が関係しており、症状の出方や程度には個人差があります。主な症状としては、気分の不安定さやイライラ、抑うつ感、頭の重さ、乳房の張り、体のむくみなどが挙げられます。こうしたPMSの症状の一環として、胃痛や胃もたれなど消化器の不快感を感じる方もいます。これは、ホルモンバランスの変化やそれに伴う自律神経の乱れが、胃腸の働きを鈍らせることが一因と考えられています。特に、胃の運動機能が低下したり、胃腸の感覚が敏感になることで、食後に胃の重さや痛みを訴えるケースがあります。月経の周期と連動して胃の違和感が繰り返し起こる場合には、PMSとの関連が疑われます。そのようなときには、ストレスの軽減や日常生活の見直しに取り組むことが有効です。症状が強く日常生活に支障が出る場合は、婦人科や内科での相談をおすすめします。
胃痛・胃もたれの検査
胃痛や胃もたれの原因として、消化管の疾患が関係していることは少なくありません。そのため、胃の内部を直接観察できる胃カメラ検査は、原因となる疾患を診断するための基本的な検査手段とされています。また、膵炎、胆のう炎、胆石症などの他の消化器疾患が原因となっているケースもあるため、必要に応じて腹部超音波検査や腹部CT検査などが行われることもあります。さらに、炎症の有無やその程度、感染の可能性などを評価するために血液検査が実施されることがあり、胸の痛みや息切れなどの症状がある場合には、心電図検査や胸部X線検査(レントゲン)によって心臓や肺の状態を確認することも検討されます。当院では内視鏡検査は実施しておりませんが、必要と判断される場合には、信頼できる連携医療機関をご紹介しております。気になる症状がある方は、まずはご相談ください。
胃痛・胃もたれがある時の対処法とは?
 まずは、胃痛・胃もたれの原因となるものを排除しましょう。
まずは、胃痛・胃もたれの原因となるものを排除しましょう。
暴飲暴食が原因の場合には、食事量を節制し、適度な量と栄養バランスのとれた食事を規則正しく摂るようにします。脂っこい物を控え、多量のアルコールや喫煙も控えましょう。
また、胃の負担を極力減らすため、食後30分間は運動や入浴などせずに、ゆっくりと過ごすことをお勧めします。
過度なストレスが原因の場合は、原因となるストレスを出来る限り取り除くようにしましょう。ストレスは、胃の働きをコントロールしている「自律神経」を乱すため、胃酸分泌を過剰にしてしまいます。胃酸分泌が過剰になると、胃もたれだけではなく、慢性的な胃炎や胃潰瘍を引き起こすため、ストレスも軽視出来ません。
なお、症状が軽い場合には、市販薬で一時的に対応することも可能です。
胃酸を抑える薬(制酸薬やH2ブロッカー)、胃の粘膜を保護する薬、消化を助ける消化酵素薬などが市販されています。ただし、症状が長引く、繰り返す、痛みが強いといった場合には自己判断での服用を続けず、早めに医療機関を受診することが大切です。
胃痛の原因がピロリ菌感染の場合は、早めに消化器内科専門医を受診しピロリ菌除菌治療を受けましょう。
生活改善をしても症状が良くならない場合
胃痛や胃もたれの原因を排除し、生活習慣を改善しても症状が持続し、良くならない場合は、何らかの大きな病気が隠れている場合があります。
胃痛・胃もたれを感じる「みぞおち」の周辺には、胃だけではなくその他の臓器もあります。胃が原因だと思っていても、実は他の臓器に由来する症状の場合もあるので、症状が持続する場合は早めに医療機関を受診しましょう。
薬物療法
胃痛の治療では、まず胃酸の出すぎが原因であることが多いため、胃酸の分泌を抑える薬が使用されます。タケキャブ(ボノプラザン)、ネキシウム(エソメプラゾール)、タケプロン(ランソプラゾール)などのプロトンポンプ阻害薬(PPI)や、ガスター(ファモチジン)などのH2ブロッカーがよく処方されます。胃の動きが低下している場合には、ガスモチン(モサプリド)やアコファイド(アコチアミド)といった消化管運動機能改善薬を併用することもあります。さらに、六君子湯や半夏厚朴湯などの漢方薬が、体質や症状に応じて使われることもあります。これらは、胃の不快感に加えてストレスや全身状態を考慮して処方されます。ストレスが大きな要因となっている場合には、抗不安薬が症状の改善に役立つこともあります。治療は、症状や体質、生活習慣に合わせて個別に行いますので、胃痛や胃もたれでお困りの方は早めにご相談ください。
ピロリ菌の除菌治療
慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍は、ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)感染が関係していることが多く、原因の特定には胃カメラ検査が重要です。胃カメラによって、ピロリ菌感染に特徴的な胃粘膜の変化が確認されることがあります。当院では内視鏡検査は行っておりませんが、必要に応じて提携する医療機関をご紹介し、検査を受けていただくことが可能です。ピロリ菌感染が確認された場合には、除菌治療として、2種類の抗菌薬と1種類の胃酸分泌抑制薬を用いた3剤併用療法(1日2回・7日間の服用)が行われます。この治療により、慢性胃炎や潰瘍の再発リスクが下がるだけでなく、将来的な胃がんの発症リスクの低減も期待できます。
胃痛・胃もたれを放置することの危険性
胃痛・胃もたれはありふれた症状ですが軽視出来ません。市販薬で対処している人も多いですが、胃痛症状には、食道がんや胃がん、胆のうがん、膵臓がんなどの命に関わる病気が隠れている可能性があります。胃痛が1ヵ月以上続く場合や、市販薬で治まった症状が服用をやめると再び悪化する時は、自分1人で解決しようとせずに、必ず医療機関を受診して正しい診断及び適切な治療を受けましょう。
よくある質問
胃もたれと胃の痛みは、どのように違うのでしょうか?
胃の痛みは、みぞおちのあたりに感じる差し込むような痛み、鈍痛、締めつけられるような感覚などを指します。一方、胃もたれは、食後に胃が重く感じる、膨らんだような不快感やムカムカするといった症状を伴います。これらの症状は、胃の運動が低下したり、胃酸が過剰になったりすることと関係しています。
胃もたれや胃の痛みが数日間続いています。病院を受診すべきですか?
1週間以上も胃もたれや胃の痛みが続いたり、繰り返したりする場合は、慢性胃炎や胃潰瘍、ピロリ菌感染などの可能性があります。とくに1ヵ月以上症状が持続する場合や、市販薬で一時的に良くなっても再発するケースでは、消化器内科での診察を受けることをおすすめします。
胃もたれや胃痛に加えて吐き気もあるとき、どんな原因が考えられますか?
急性胃炎や胃腸炎、機能性ディスペプシア、食中毒、膵炎、胆のうの炎症などが疑われます。とくに吐き気が強い、繰り返し嘔吐するなどの症状がある場合は、消化管や臓器に異常がある可能性もあるため、早めの医療機関の受診が望まれます。
胃が「キューッ」と痛くなるのはなぜですか?
キリキリ、キューッとした胃の痛みは、胃酸の分泌過多や自律神経の乱れ、胃の動きの異常などが背景にあることが多く、機能性ディスペプシアやストレス性胃炎によく見られます。痛みが繰り返す、または強い場合は、検査で原因を調べる必要があります。
急性胃炎の初期には、どのような症状が出ますか?
急性胃炎の初期には、みぞおちの痛み、吐き気、胃のムカつき、食欲不振などの症状が現れます。原因としては、過度な飲食やアルコール、鎮痛薬(NSAIDsなど)、細菌やウイルスの感染が挙げられます。早期の対処が症状の悪化を防ぐ鍵となります。
急に強い胃の痛みが出た場合、どんなことが考えられますか?
突然の激しい胃痛は、アニサキス症、胆石の発作、膵炎、胃潰瘍の穿孔、胃がんなどの可能性があります。特に吐き気や嘔吐、発熱、吐血、黒色便(タール便)がある場合は、すぐに医療機関を受診してください。
ストレスが原因の胃炎にはどんな症状がありますか?
ストレス性胃炎では、胃のムカムカ感、みぞおちの痛み、食欲の低下、胃の張りといった症状が見られます。ストレスにより自律神経が乱れると、胃酸が過剰に分泌されたり、胃の動きが悪くなったりして、これらの症状を引き起こします。
ピロリ菌に感染すると、どんな不調が起こるのですか?
ピロリ菌に感染すると、慢性胃炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍などの原因になります。胃の痛みや胃もたれ、食欲不振などの症状が見られることもありますが、初期には無症状であることも多いため、胃カメラによる検査が推奨されます。
胃が痛むときは、どのように対処すればよいですか?
まずは安静にし、脂っこいものや香辛料などの刺激物を控え、消化の良い食事を心がけましょう。軽い症状であれば、市販の胃薬(胃酸を抑える薬や胃粘膜を保護する薬)で対応できることもありますが、症状が長引く場合は、医療機関を受診しましょう。
胃の痛みがあるときに、ロキソニンやカロナールなどの市販薬を飲んでも問題ありませんか?
ロキソニンなどのNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)は胃の粘膜に負担をかけるため、胃痛があるときには服用を避けましょう。一方で、カロナール(アセトアミノフェン)は胃に比較的やさしいとされていますが、使用する際は医師や薬剤師に相談するようにしましょう。