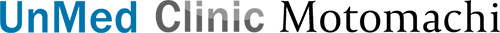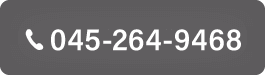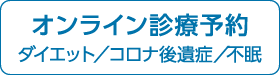体重減少
 体重減少については、食欲低下に伴うものと食欲はあるのに体重が減少するものとあり、ダイエットなどの意図的な体重減少ではなく、1年で10%以上もしくは半年で5%以上の体重減少を認めた場合は、何らかの疾患が隠れていることが懸念されるため、しっかりとした評価が重要です。
体重減少については、食欲低下に伴うものと食欲はあるのに体重が減少するものとあり、ダイエットなどの意図的な体重減少ではなく、1年で10%以上もしくは半年で5%以上の体重減少を認めた場合は、何らかの疾患が隠れていることが懸念されるため、しっかりとした評価が重要です。
体重減少率とBMI
体重の変化がどの程度かを判断する際には、「体重減少率」という数値を用いるのが一般的です。体重減少率は、次の式で求められます。
「(体重減少率)=(通常の体重 − 現在の体重) ÷ 通常の体重 × 100」
たとえば、普段の体重が60kgだった方が、現在の体重が56kgになっていた場合、
体重減少率は、「(60 − 56) ÷ 60 × 100 = 6.7%」となります。
この減少率が5%以上の場合は、医学的に「病的な体重減少」とみなされることが多く、2〜3%程度の減少であれば「軽度の体重減少」と考えられます。
なお、体重減少率が5%未満であっても、BMIが低い方では、健康上の問題が隠れている可能性があります。特に、BMIが18.5未満のやせ型の体格に該当する方は、体重がさらに減ることで栄養不良を引き起こしやすいため、慎重な観察が求められます。
BMI(Body Mass Index)は、身長と体重をもとに算出される指数で、体型や栄養状態を評価するための代表的な指標として広く用いられています。BMIは、次の式で求められます。
「BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m)」
たとえば、体重が50kgで身長が1.60mの方の場合、
BMIは「50 ÷ 1.60 ÷ 1.60 = 19.5」となります。
日本肥満学会の基準による、BMIの分類は以下の通りです。
- 18.5未満:低体重(やせ)
- 18.5〜24.9:標準
- 25以上:肥満
また、健康的な体型の基準の「適正体重」はBMI 22を基準として計算されるのが一般的です。
日常生活から考えられる原因
ダイエットによる食事量の減少
ダイエットのために食事量を減らしたり、低カロリー食ばかり摂取していると、体の脂肪や筋肉が減り体重は減少します。しかし、極端なダイエットは、神経性食欲不振症(拒食症)に繋がってしまったり、栄養バランスが著しく偏り、体の機能を正常に働かせるために必要なビタミンやミネラルが不足し、健康を維持出来なくなることもあり、体に様々な障害を引き起こします。
精神的ストレス
緊張や不安など精神的ストレスが長期的に続くと、交感神経が持続的な興奮状態になり、消化吸収を促進する副交感神経の働きが抑制されます。その結果、食欲がわきにくくなり、食事の量が減って体重が落ちていきます。また、ストレスが原因で胃炎や胃潰瘍、慢性的な下痢が起こる場合も多く、その影響で食事量が減るだけでなく、正常に消化吸収出来なくなることによって十分な栄養が体に取り込まれず、結果として体重減少につながることがあります。
エネルギーの過剰消費
激しいスポーツでエネルギーを過剰に消費したり、仕事で体を酷使していると、多くの栄養分を身体のエネルギーとして利用するために必要な栄養素が不足気味となり、消耗して体重が減少することがあります。
加齢
加齢に伴い、私たちの体のさまざまな機能は徐々に衰えていきます。高齢になると、筋肉量や骨量の減少(サルコペニア)に加えて基礎代謝が下がり、食欲や胃腸の働きも弱まりやすくなります。その結果、消化不良や栄養の吸収不良が起こり、病気がなくても体重が少しずつ減っていくことがあります。また、味やにおいを感じにくくなる、噛む力や飲み込む力が低下するといった変化により、食事が負担に感じられ、自然と食事量が減ることもあります。さらに、一人暮らしや身体機能の低下によって、栄養バランスのとれた食事を用意するのが難しくなることも、体重減少の要因のひとつです。
薬剤の副作用
薬の影響で食欲が低下したり、消化不良を起こしたりすることで、体重が減少することがあります。たとえば、抗うつ薬、抗がん剤、糖尿病治療薬(GLP-1受容体作動薬など)では、吐き気や下痢、食欲不振などの副作用により、食事量や栄養の吸収が減ることで体重が落ちる場合があります。また、利尿薬や神経系の薬(抗けいれん薬、認知症治療薬など)は、水分代謝やエネルギーの消費に影響し、体重の変動を引き起こすことがあります。薬の服用中に体重が減ってきたと感じたら、自己判断でやめずに医師へ相談することが大切です。薬の種類や量を調整することで、副作用が改善されることもあります。
便秘・胃もたれ
便秘や胃もたれなどの消化機能の不調も、体重が減る原因のひとつになることがあります。たとえば、便秘が続くと、お腹の膨満感や不快感が食欲に影響し、結果的に食事量が減ってしまうことがあります。また、胃もたれが慢性的にある場合には、少し食べただけでもすぐに満腹感を感じてしまい、必要な量の栄養を摂取しにくくなることがあります。これらの状態は、加齢やストレス、食生活の乱れなどによって起こることが多く、長く続くと栄養不足や体重減少につながるリスクがあります。
体重減少を伴う疾患
神経性食欲不振症(拒食症)
やせ願望や肥満に対する恐怖心から極度の食事制限や、食後に食べた物を吐く習慣、さらには下剤の乱用などによって20%以上も体重が減少することがあります。ダイエットや胃腸症状・食欲不振を契機に発症します。体重や体型の認知が歪んでいて、実際は痩せているのに太っていると感じ、少しでも体重が増えると際限なく増えると考えます。女性の場合は3カ月以上無月経が続くこともあります。思春期の女性に多く、普段は元気で活動的なのが特徴ですが不整脈を起こして突然死することもあります。
がん(胃がん、大腸がん、膵臓がんなど)
消化器臓器に癌が発症し進行すると、がん細胞に多くの栄養分が奪われるようになり、また正常な消化吸収機能が果たせなくなり、さらには正常組織とがん細胞との間で炎症も起こるため、腹痛や発熱や食欲不振、さらには体重減少といった症状を認めるようになります。初期段階では、症状を認めないことが多いため、早期発見・早期治療のためにも健康診断等で定期的な検査を受けることが大切です。また、原因不明の体重減少を認めた場合は、がんの発症を念頭に直ぐに医療機関を受診することをお勧め致します。
糖尿病
膵臓から分泌されるインスリンの量や作用が低下し、血糖値が慢性的に高い状態になる生活習慣病です。食事から摂取した糖質をエネルギーとして利用出来なくなり、代わりに脂肪や筋肉中の蛋白質が分解されてエネルギー源として利用されるため、体重が減っていきます。肥満や老化、遺伝が発症に関係していると考えられています。
うつ病
身体に何らかの病気が無いにも関わらず、慢性的にだるさや疲れがあり、気力が低下し落ち込んでしまい、興味や楽しい気持ちを失い、その状態から自力で回復することが難しくなる精神疾患です。多くの場合、食欲が減退し体重も減少します。その他、睡眠障害、集中力の低下、体の動きが鈍ったり、逆にイライラして焦る気持ちが強くなったりなどの症状が現れます。
甲状腺機能亢進症(バセドウ病)
甲状腺ホルモンが過剰に分泌される疾患です。新陳代謝が亢進されるために、常に運動しているような状態になり身体が消耗します。食欲があってたくさん食べているにもかかわらず、それ以上にエネルギーを消費することから痩せていきます。疲れやすくなり、汗を多くかくようになり、下痢をしやすくなります。また、精神的に落ち着かなくなりイライラすることや不眠などの症状が出ることもある。甲状腺の腫れや眼球の突出、手のふるえ、動悸などの症状もあらわれます。
自己免疫の異常や遺伝が関係していると考えられ、多くは20〜30代の女性に発症しますが、男性の発症もめずらしくありません。自律神経失調症や更年期障害に似た症状が多いため間違えやすいですが、放置しておくと心不全など命にかかわる症状が現れることもあり、適切な治療を受けることが大切です。
潰瘍性大腸炎・クローン病
潰瘍性大腸炎・クローン病は、どちらも腸に慢性的な炎症を引き起こす炎症性腸疾患(IBD)に分類されます。潰瘍性大腸炎は、大腸粘膜にアフタや潰瘍ができる炎症性疾患で、ここ数年患者数が急増しています。20代の若い人に多く発症し、非常に再発しやすいという特徴があります。主な症状として、下痢にともなう粘血便が現れ重症化すると発熱や腹痛が生じます。長期間下痢が続くため、体重減少が見られることが多くあります。クローン病も同様に若年層に多く、口から肛門までの消化管のどこにでも炎症や潰瘍を起こす可能性がある疾患です。特に小腸や大腸に炎症が起こりやすく、腹痛、下痢、発熱、倦怠感、体重減少などが慢性的に続くことがあります。腸管の炎症による吸収不良や食欲低下が重なることで、栄養不足から体重が大きく減るケースもあります。
慢性膵炎
膵臓は、脂質やたんぱく質などの栄養素を分解・吸収する消化酵素を分泌する臓器です。慢性膵炎になると膵臓の機能が徐々に低下し、消化不良や吸収不良が起こりやすくなります。その結果、食事をしていても栄養が十分に吸収されず、体重が減少することがあります。また、腹痛や不快感などの症状により食欲が落ち、食事量が減ることも体重減少の一因となります。慢性的な飲酒や喫煙、ストレスが関係することもあり、早期の受診が勧められます。
吸収不良症候群
身体に必要な栄養素や水分を吸収出来ない障害があるために、栄養が不足して体重が減少します。その他、慢性的な下痢、全身のむくみ、貧血、口内炎などを引き起こします。また、脂肪の吸収不良より脂肪分を多く含んだ脂肪便が排出されます。
通常の便は便器の水の中に沈みますが、脂肪便は浮くのが特徴です。
機能性ディスペプシア
機能性ディスペプシア(FD)は、検査で明らかな異常がないにもかかわらず、胃の不快感や膨満感、もたれ、胃痛などが続く疾患です。胃の動きの低下や知覚過敏により、少量でもすぐ満腹になる「早期膨満感」や慢性的な胃もたれが起こり、食事量が減って体重が徐々に落ちていくことがあります。ストレスや自律神経の乱れも症状を悪化させやすく、体重減少が続く場合は、他の消化器疾患との鑑別のためにも早めの受診が勧められます。
逆流性食道炎
逆流性食道炎は、胃の内容物が胃酸とともに食道へ逆流し、食道の粘膜が炎症を起こす疾患です。胸やけや胃もたれ、喉の違和感といった不快な症状が続くと、食事のたびに不快感を感じやすくなり、食欲が低下することがあります。その結果として、食事量が減少し、体重が少しずつ減っていく場合があります。
慢性胃炎、胃・十二指腸潰瘍
慢性胃炎は、急性胃炎を繰り返すことやピロリ菌感染によって胃粘膜障害が慢性化することが原因です。長期的なストレスも要因となります。
胃・十二指腸潰瘍は、慢性的なストレス、ピロリ菌感染、解熱鎮痛剤の過量服用などによって起こります。過剰な胃酸や薬の刺激が胃・十二指腸の粘膜を傷つけ、それが長く続くと潰瘍ができます。
食道アカラシア
食道アカラシアは、食道と胃のつなぎ目にある筋肉がうまく開かず、食べ物が胃に届きにくくなる疾患です。食道の動きも弱まるため、食べ物が停滞しやすく、胸のつかえ感や飲み込みにくさ、逆流、胸痛などが起こります。液体のほうが飲みにくいのが特徴です。食事が思うようにとれず、摂取量が減ることで体重が徐々に減少します。進行すると栄養不足や脱水のリスクがあるため、症状が続く場合は早めの受診が勧められます。
体重減少の検査
体重減少の背景には、内分泌異常や消化器の不調、精神的ストレス、薬の影響など、さまざまな要因が関係している可能性があります。そのため、まずは問診によって、症状の経過や服用中の薬、食欲の変化、生活習慣、ストレスの有無などを丁寧に確認します。その上で、体重減少の原因を的確に鑑別するために、以下のような検査を必要に応じて実施します。
- 血液検査:炎症や貧血、肝機能・腎機能、甲状腺ホルモン、電解質バランス、腫瘍マーカーなどを評価します。
- 尿検査:糖尿病や腎疾患の有無を調べます。
- 腹部レントゲン検査:腸管ガスの状態や便の停滞などを確認します。
- 腹部超音波検査(エコー):肝臓・膵臓・胆のう・腎臓などの臓器の異常を確認します。
- CT検査・MRI検査:臓器の構造異常や腫瘍、炎症、リンパ節腫大の有無を詳しく調べます。
- 胃カメラ検査:逆流性食道炎、食道アカラシア、胃潰瘍、胃がんなどの有無を確認します。
- 大腸カメラ検査:潰瘍性大腸炎、クローン病、大腸がんなどの腸疾患を評価します。
なお、当院では内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)は行っておりませんが、必要と判断した場合には、提携する医療機関をご紹介いたします。体重減少は、重要な疾患の兆候であることもあるため、原因を早期に鑑別し、適切な治療につなげることが大切です。気になる症状が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
体重減少の治療
体重減少の治療では、まず原因となる疾患を正確に鑑別し、それに応じた適切な治療を行うことが基本です。検査で内科疾患や消化器疾患などが判明した場合には、早期に治療を開始することで、食欲や栄養状態が改善され、体重も徐々に回復するケースが多くみられます。一方で、各種検査を行っても明らかな異常が見つからない場合には、ストレスや心理的要因が関係している可能性があります。その際は、ストレス軽減や睡眠の質の改善、栄養バランスのとれた食生活の見直しなど、生活習慣の調整が治療の中心となります。それでも不安や不眠、気分の落ち込みが続くようであれば、必要に応じて睡眠導入薬や抗不安薬、抗うつ薬の使用を検討することもあります。精神的な負担が軽くなることで食欲が回復し、体重減少の改善につながることがあります。いずれにしても、体重減少が続く場合は早めに原因を探り、心身の状態に応じた対応を行うことが重要です。
日常生活で出来る対策
ストレスを溜めないようにする
スポーツや趣味など、自分に合ったストレス解消法を見つけることも大切です。また、質の良い眠りは、ストレス軽減にとても大切です。40℃以下のぬるめのお湯にゆったりとつかってリラックスしたり、寝る前に軽いストレッチを行うなど、なるべく深い眠りが得られるように工夫しましょう。
睡眠習慣の見直し
毎日同じ時間に寝起きする習慣をつけることや、就寝前のスマートフォンやパソコンの使用を控えること、寝室の明るさ・室温・湿度を快適に保つことが、質の良い睡眠につながります。また、日中に軽い運動を取り入れたり、就寝前にぬるめのお湯で入浴することも、自然な眠りを促進する方法として有効です。
無理なダイエットや極端な偏食を避ける
たんぱく質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラルを毎日の食事の中でバランス良く摂取しましょう。
よくある質問
ステロイドを使用しているのに体重が減少するのはなぜですか?
ステロイド薬には通常、食欲を高める作用があるため、体重が増加するケースが多く見られます。しかし、それにもかかわらず体重が減る場合には、いくつかの背景が考えられます。たとえば、基礎にある膠原病や呼吸器疾患などが悪化していると、全身状態の悪化によって体重減少が起こることがあります。また、ステロイドによって消化機能に不調をきたし、胃の不快感や下痢、栄養素の吸収障害が生じる可能性もあります。さらに、ステロイドの長期使用により筋肉量が減る「ステロイドミオパチー」や、ストレスなどの心理的要因も体重の減少に影響を及ぼします。このような変化が見られた際には、薬を自己判断で中止するのではなく、主治医に相談し、必要に応じて検査や処方内容の見直しを行うことが重要です。
妊娠後期に体重が減るのは正常ですか?それとも何か原因がありますか?
妊娠後半になると、子宮の増大によって胃が圧迫され、食事量が減ることで体重がわずかに減少することがあります。これは一時的なものであり、必ずしも異常とは限りません。ただし、著しい体重の減少や倦怠感、むくみといった症状がある場合には、妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病、胎児発育不全などの疾患が隠れていることも考えられます。定期的な妊婦健診で体重の推移を確認し、異常があればすぐに医師に相談しましょう。
喘息の持病がある場合、体重減少の原因になることはありますか?
喘息そのものが直接的に体重減少を引き起こすことはあまりありませんが、重症のケースでは慢性的な呼吸困難、不眠、ステロイド吸入の影響で消化器の不調が生じることがあり、間接的に体重が落ちる要因となることがあります。また、繰り返す発作や活動制限によって筋力が低下し、基礎代謝に影響を及ぼすことも考えられます。急激な体重減少がみられる場合は、慢性閉塞性肺疾患(COPD)や感染症などの合併症を含めた評価が必要です。
貧血が体重減少の原因になることはありますか?
鉄欠乏性貧血などの一般的な貧血では、体重減少を直接引き起こすことは少ないとされています。しかし、貧血が重度になると倦怠感や食欲不振が起こり、結果として体重が減ることがあります。また、貧血と同時に消化管からの出血や栄養吸収障害などが存在する場合、それらが体重減少の要因となる可能性もあります。両者が同時に見られるときは、消化器内科での精査を検討しましょう。
小学生の子どもが体重減少しているのですが、どんな原因が考えられますか?
小児の体重減少は、摂取カロリーの不足、感染症(風邪や胃腸炎が長引く場合など)、アレルギー疾患、糖尿病、小児がん、摂食障害など、さまざまな原因が考えられます。また、学校生活や家庭環境でのストレスが影響していることもあります。急激な体重の減少や、倦怠感、顔色の変化、発熱、腹痛といった症状がある場合は、小児科での早期の診断と対応が重要です。
痩せすぎはどこから?
一般的には、BMI(体格指数)が18.5未満である場合、「低体重(痩せ)」とされます。さらにBMIが17.0を下回ると、栄養不良や内科的な問題が潜んでいる可能性があるため、医師による評価が望ましいです。無月経、疲労感、筋力低下などの症状がある場合には、早めに専門医の診察を受けることが大切です。
体重の減少ががんの初期症状として現れることはありますか?
はい、体重の減少は消化器系のがん(胃がん、大腸がん、膵臓がんなど)で初期症状として現れることがあります。特に、はっきりとした原因がないのに急激に体重が落ちている場合は、がんの可能性を考慮する必要があります。がんの初期段階では自覚症状が乏しいことも多く、体重減少が唯一のサインであることもあるため、早期の精密検査が重要です。
急激な体重減少を引き起こす疾患には何がありますか?
急に体重が落ちる場合、以下のような疾患が関連していることがあります。
- 甲状腺機能亢進症(バセドウ病)
- 糖尿病(とくに1型)
- 神経性食欲不振症(拒食症)
- 消化器がん、膵臓がん
- 潰瘍性大腸炎、クローン病
- 慢性膵炎、吸収不良症候群
- 重度のうつ病
これらの疾患は、早期に診断し治療することが重要です。
体重が継続的に減っていくような疾患には何がありますか?
徐々に体重が減少していく場合、以下のような慢性疾患が考えられます。
- 慢性膵炎
- 吸収不良症候群
- 機能性ディスペプシア
- 慢性胃炎や胃・十二指腸潰瘍
- 慢性心不全や慢性腎不全
- 結核などの慢性感染症
- うつ病や慢性のストレス状態
これらの疾患では、時間をかけて体重が落ちていくため、継続的な経過観察と適切な診療が必要です。
ストレスによる体重減少にはどのような特徴がありますか?
ストレスが原因で体重が減る場合には、以下のような特徴が見られます。
- 特定の身体疾患が見当たらない
- 食欲不振、不眠、気分の落ち込みが併発する
- 胃の不快感や吐き気、下痢などの自律神経症状が現れる
- 数日ではなく、数週間〜数ヵ月かけてゆっくりと減少していく
日常生活の変化や仕事・人間関係による心理的なストレスが背景にあることが多く、必要に応じて心療内科や精神科での対応が求められます。
食事量が変わらないのに体重が減る場合は、何科を受診すべきですか?
食事の量が以前と変わらないにもかかわらず体重が減っている場合は、まず内科を受診することが適切です。診察の結果に応じて、以下のような専門科への紹介が検討されます。
- 消化器内科(消化吸収障害や悪性疾患の可能性)
- 内分泌内科(甲状腺や糖代謝の異常)
- 精神科・心療内科(心理的ストレスやうつ状態)
まずは内科で総合的に診断を受けることが、適切な対処につながります。